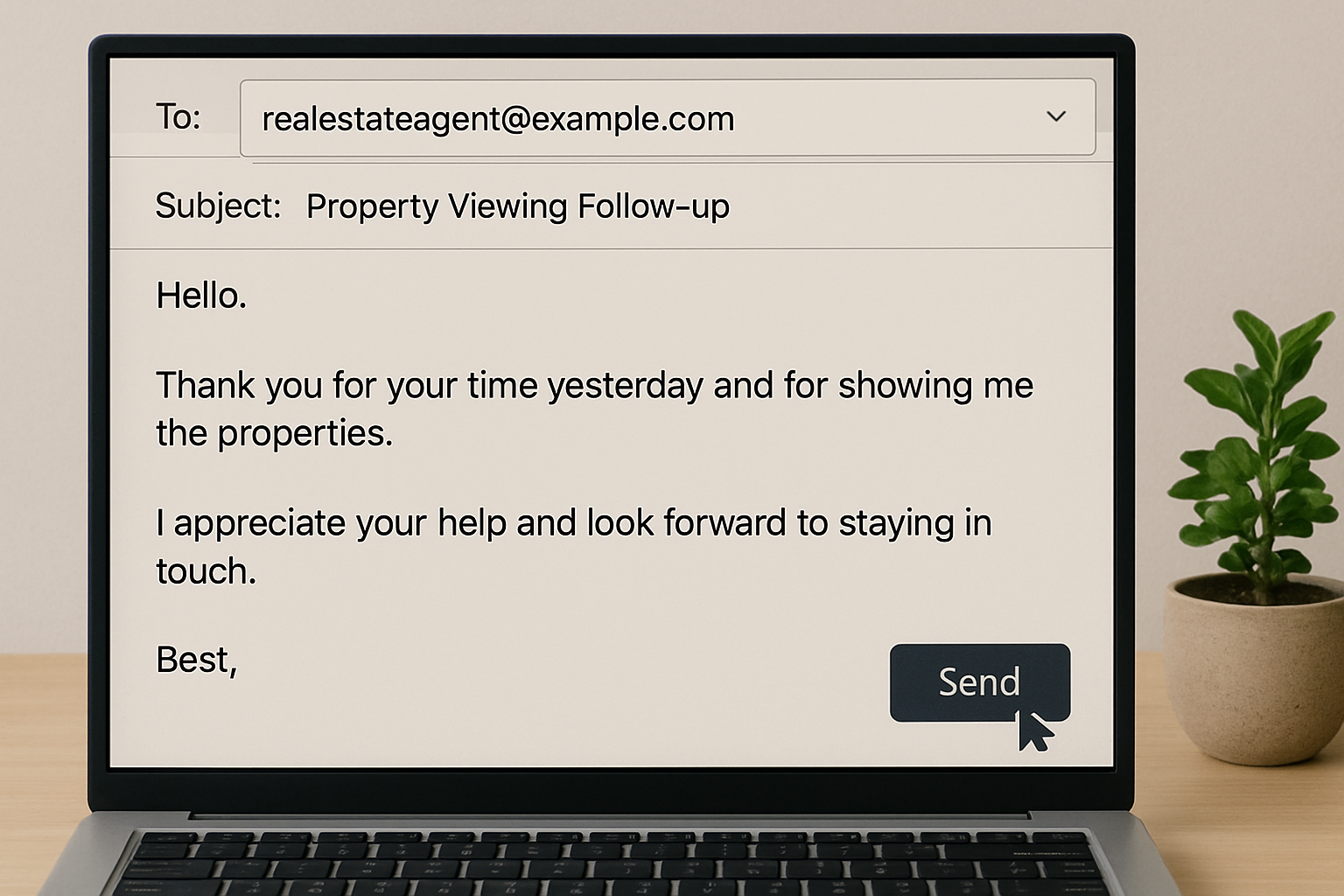「2025年問題」とは、2025年に日本の団塊の世代(1947~49年生まれ)の全員が75歳以上の後期高齢者になることによって生じる社会的課題の総称です。高齢者人口の急増に伴い介護・医療費など社会保障負担の増大や労働力人口の減少が懸念されており、不動産市場にも大きな影響を及ぼすとされています。具体的には相続発生件数の増加、住宅を購入・賃借する側の需要低下、そして住宅ストックの空き家増加などが起こると考えられています。これらの構造的な変化により、「不動産価格が大暴落するのではないか」という極端な見方も一部で報じられています。しかし専門家によれば、人口減少・高齢化が原因で2025年に突然不動産価格が急落することは考えにくく、むしろ長期的に緩やかな影響が出ると見られています。いずれにせよ2025年前後は不動産市場の転換点となり得るため、不動産オーナーにとって注意深い状況分析が必要な時期と言えます。
サブリース契約の仕組みと地方における問題事例
こうした環境変化の中、不動産オーナーの間で特に懸念されるのが「サブリースアパート2025年問題」です。まず、サブリース契約(いわゆる一括借り上げ)とはどのような仕組みか整理します。サブリースとは、不動産管理会社などの業者がオーナーから賃貸物件を一括して借り上げ、第三者に転貸する契約形態です。オーナー側には「空室リスクを気にせず一定の賃料収入が得られる」「賃貸経営の手間が省ける」といったメリットがあり、特に初心者や消極的オーナーにとって魅力的な仕組みです。しかしその一方で、サブリース特有のリスクやトラブルも存在します。実際、「30年一括借り上げで長期安定収入」といったセールストークを信じて契約したものの、後になって賃料の大幅減額を提示されたり、挙句には賃料不払いに陥ったりするケースが各地で報告されています。独立行政法人国民生活センターによると、2022年度に全国の賃貸住宅(集合住宅・分譲マンション)契約に関する相談は1,337件にのぼり、その中には「サブリース会社から賃料が支払われなくなった」「契約を解除できず違約金を請求された」といった苦情が含まれています。契約上オーナー側から中途解約や物件売却が容易でないケースも多く、賃料減額に応じなければ業者から契約打ち切りを持ちかけられるなど、オーナーが身動きの取れない状況に陥る例も見られます。
このようなサブリースを巡るトラブルは、特に人口減少が著しい地方圏で顕在化してきました。地方の地主が相続税対策でアパート建設を行いサブリース契約を結んだものの、入居者不足で採算が合わず賃料保証の引き下げを迫られる、といった事例が各地で発生しています。国土交通省や消費者庁も問題視し、2020年12月にはサブリース新法(賃貸住宅管理業法の改正)が施行されました。これによりサブリース契約時には業者に重要事項説明書の交付が義務付けられ、誇大な勧誘や「長期家賃保証」をうたう誤認広告の禁止など、一定の規制措置が講じられています。こうした行政の対策にもかかわらず、依然として上記のようなサブリース巡るトラブルは後を絶たないのが現状です。
過去に注目を集めた問題事例としては、次のようなケースがあります。ひとつは大手サブリース業者レオパレス21による契約賃料の一方的な引き下げ問題です。レオパレス21社では2018~2019年にかけて施工不良問題が発覚し、多数の管理物件で入居者退去や修繕が必要となりました。その結果、同社の経営が行き詰まりオーナーへの賃料保証を維持できなくなったため、「最長30年一括借り上げ」の宣伝文句で契約したオーナーに対して次々と賃料減額を通知する事態となりました。一部のオーナーは「話が違う」として訴訟を起こしましたが、契約書上は賃料見直し条項が盛り込まれているケースが大半であり、オーナーにとって厳しい状況となっています。また別の例として、有名な「かぼちゃの馬車」事件があります。この事件では、女性向けシェアハウス「かぼちゃの馬車」を展開していた不動産会社スマートデイズ社が、オーナーに対し「30年間家賃保証」をうたって物件を販売・サブリース契約を締結しましたが、2018年に同社が経営破綻し賃料支払いが停止。多くのオーナーが物件購入のため融資を受けていたため、家賃収入が途絶えたことでローン返済が不能となり、自己破産に追い込まれるという深刻な被害が生じました。このように、地方・都市問わずサブリース契約には契約当初の想定と異なるリスクが潜んでおり、不動産オーナーにとって他人事ではない問題となっているのです。
首都圏でもサブリース2025年問題は起こり得るのか?
では、これまで主に地方で顕在化してきたサブリース賃料引き下げ問題が、人口集積が進む首都圏でも起こり得るのでしょうか。結論から言えば、「首都圏でも無視できない」というのが私の見解です。サブリース業者の中には「首都圏なら将来も人口が減らないから大丈夫です」と営業トークに乗せる例もありますが、これは一面的な説明に過ぎません。確かに東京圏全体の総人口は2025年以降もしばらく緩やかに増加・横ばいが続き、東京都の人口減少は2045年頃まで始まらないとの予測もあります。しかし、サブリース経営の安定性を判断するには人口の絶対数よりも中身(構成)を見る必要があります。賃貸住宅の主な借り手層は大学生や単身勤労者などの20~40代人口であり、この層の動向が賃貸需要を左右します。東京都の場合、総人口は今後もしばらく高齢者増加で支えられるものの、肝心の20~40代の人口は既に減少局面に入ると予想されています。実際、将来推計では首都圏(主に1都3県)における20~49歳の人口は2025年に約12%減少すると見込まれており、東京圏でも若年~生産年齢層の減少による賃貸需要の縮小は避けられない状況です。さらに首都圏といえど地域差も大きく、東京都内でも都心部と周縁部で人口動態は明暗が分かれます。例えば23区内でも「千代田区」「中央区」「港区」など都心・湾岸エリアは若年人口が増加傾向で2045年頃まで現状より人口が増える予測ですが、一方で「足立区」「江戸川区」など郊外寄りの区では2045年に現在より若年層人口が15%以上減少すると推計されています。東京都下の多摩地域では減少率30~40%に達する市もあり、2025年時点で20~40代人口が現状より増えている地域はごく一部の中心エリアに限られるというのが実情です。このように、仮に首都圏全体の人口が維持されていても、その内訳の変化や地域偏在により賃貸需要の減退は避けられず、首都圏であってもサブリース賃料の引き下げリスクを楽観視できないことがわかります。
加えて、首都圏の住宅供給動向にも目を向ける必要があります。2015年の相続税改正以降、都心近郊でも節税目的のアパート建設が活発化し、新築賃貸住宅の供給が増えました。さらに東京オリンピック(2020年)前には都内各地で再開発・建設ラッシュが起こり地価が高騰しましたが、その反動による市況悪化も危惧されています。新築マンション・アパート供給が一巡した2020年代半ば以降は、賃貸住宅の競争激化が予想されます。現に足元では、都市部を中心に不動産価格が高止まりしている一方で、全国的な空き家総数と空き家率は過去最高を更新しており、空室の増加傾向が顕著です。
総務省「住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家数は1978年の約276万戸(空き家率7.6%)から右肩上がりに増加し、直近の2023年時点では約900万戸、空き家率13.8%に達しています。この黒線グラフ(空き家率の推移)が示す通り、日本全体で住宅の余剰化が進み、「4軒に1軒が空き家になる」とも言われる時代が現実味を帯びつつあります。都市部においても例外ではなく、人口減少や核家族化により相続された住宅がそのまま空き家になるケースが増えており、賃貸用住宅も含め空室率の上昇が懸念されます。賃貸マーケットでは空室が増えれば家賃相場に下押し圧力がかかるため、賃料水準の低下という形でもサブリース業者・オーナーに影響が及ぶでしょう。特に築年数の経った物件ほど空室リスクが高まりやすく、築古物件しか供給のない地域では需給バランスが崩れやすくなります。以上のような賃貸需要の減少(人口動態)と住宅供給過多(空室率上昇)の背景から、首都圏でもサブリース契約の収支悪化リスクが高まると考えられます。
最後に、2025年前後のタイミングに注目すべき要因があります。それは、前述のように2015年前後に契約・建設されたサブリース物件が築10年を迎える節目だという点です。サブリース契約では一般的に契約開始から数年~10年間程度は家賃保証額が固定され、その後契約更新時に賃料見直しが行われるケースが多く見られます。築10年を超える頃から物件の魅力(新しさ)が薄れ始め、入居付けのために家賃を下げざるを得なくなる傾向があるためです。同時に設備修繕など維持コストも増加し、サブリース業者にとっては契約当初に見込んだ利幅が圧迫されやすい時期でもあります。その結果、10年目以降に賃料引き下げ交渉が頻発することは業界内でもよく知られています。実際、2025年前後に築10年を迎える物件ではこのタイミングで賃料見直しが行われ、サブリース業者から大幅な家賃保証額の減額要求が起こると予想されています。さらに先述した賃貸需要の減退(団塊世代の高齢化による借り手減少)が追い打ちをかけ、業者からの減額圧力はいっそう強まる見通しです。つまり、2025年問題の波は首都圏のサブリース物件にも押し寄せる可能性が高いと言えます。特に2015年以前に建築された物件(2025年に築10年以上となる物件)をお持ちのオーナーの方は、今後の動向に十分な注意が必要です。
2025年に向けて不動産オーナーが取るべき対策
以上を踏まえ、2025年問題によるサブリース契約リスクに備えて不動産オーナーが取り得る具体的な対策を考えてみます。将来の不安要素が高まる局面だからこそ、受け身ではなくオーナー自ら積極的にリスク管理・戦略見直しを行うことが重要です。以下に主なポイントを挙げます。
-
サブリース契約内容の再確認
現在サブリース契約を結んでいるオーナーは、まず契約書の内容を改めて確認することが肝要です。契約期間中に賃料改定が可能な条件やタイミング、オーナー側から契約解除できる要件(違約金の有無など)を把握しておきましょう。特に更新時期が近い場合、賃料減額交渉の余地や手続きについて事前に理解し、必要に応じて専門家(不動産コンサルタントや弁護士)に相談することをおすすめします。契約内容によっては減額に同意しなければ契約打ち切りもあり得るため、最悪のシナリオも織り込んだ対応策を検討しておくべきです。また、業者側から提示される新条件に納得できない場合に備え、代替プラン(例えば他の管理委託方式への切り替えや、自主管理への移行など)も視野に入れておくと安心です。契約事項の再確認と情報収集は、オーナー自身がリスクに備える第一歩と言えるでしょう。 -
収益のリスク分散と資産ポートフォリオ見直し
サブリース物件に限らず、不動産投資全般において収益源の分散は基本的なリスク管理策です。特定の物件や特定エリアの賃料収入に依存しすぎていないか、自身の資産ポートフォリオを点検してください。例えば、サブリース契約の物件収入が家賃収入全体の大部分を占めている場合、想定以上の減額があれば家計やローン返済に直結する恐れがあります。その対策として、他の収入源を確保したり、複数の小規模物件に分散投資したりすることが考えられます。また、不動産以外の資産(預貯金や有価証券など)とのバランスも重要です。一つのリスク要因で家計全体が傾かないよう、資産全体を長期的視点で再構築することを検討しましょう。なお、新たに不動産投資を行う場合は、安易にサブリースの魅力だけに飛びつかず、本来得られるべき利回りとサブリース手数料等のコストを冷静に比較検討する姿勢が求められます。サブリースを利用しなければ得られるはずの収益(空室リスクを自分で負う代わりに受け取れる家賃や礼金等)にも目を向け、必要以上に業者任せにしないこともリスク分散の一環と言えるでしょう。 -
エリア戦略・物件戦略の見直し
サブリース2025年問題の根底には人口減少と需要減退という構造問題がありますが、その影響度合いは地域や物件特性によって大きく異なります。したがって、オーナーは保有物件のエリア特性や市場競争力を今一度見直す必要があります。もし物件が将来的に賃貸需要の先細りが懸念される地域(例えば人口減少が著しい郊外エリアや駅から遠い立地など)にある場合、対策として入居者ニーズに合わせた設備投資やリノベーションで競争力を高めることが考えられます。それでも空室が埋まらないようであれば、思い切って賃料水準の見直し(家賃の引き下げ)を行い、市場ニーズに適合させることも検討すべきでしょう。逆にこれから不動産投資を継続する場合は、物件選定基準の厳格化が求められます。サブリースに頼るにせよ自力運営するにせよ、需要の底堅いエリアや物件を選ぶことが長期安定の近道です。多少初期投資額が高く利回りが低下しても、都心の駅近など好立地物件にこだわる価値はあります。実際、都心部の優良エリアは賃貸需要が落ちにくく、市況悪化時でもテナント確保が比較的容易です。反対に人口減少の激しい地域では、どれほど条件が良くても空室率の上昇には抗い難いものがあります。現在の保有物件の収益シミュレーションをアップデートし、地域の人口動態や競合物件数、将来の再開発計画などの情報を収集して、今のエリア戦略を再点検してください。必要であれば物件の入替え(売却して別エリアで再投資)も視野に入れ、将来を見据えた柔軟な戦略修正を行うことが大切です。 -
出口戦略(売却・活用法)の検討
長期保有を前提に賃貸経営を始めても、状況次第では適切なタイミングで資産を手放す決断も必要です。サブリース契約物件に関しても、将来的に収支悪化が避けられないと判断した場合は、早めの売却や活用方法の転換を検討しましょう。特に家賃保証の減額提示を受けた場合、「収益悪化に陥ったが契約上すぐには解除も売却もできない」という事態に直面しがちです。そうなる前に、市場環境が比較的良好なうちに売却するのも有力な選択肢です。近年はサブリース物件専門の買取業者や相談サービスも登場しており、実際にサブリース契約や物件売却に関する無料相談を提供する企業もあります。売却だけでなく、例えば住宅系から高齢者施設やシェアハウス等への用途変更によって新たな需要を取り込む道も考えられます(ただし用途変更する場合はサブリース契約の解除または見直しが前提となります)。いずれにせよ、出口戦略を予め用意しておくことで、予期せぬ事態にも損失を最小限に抑える判断が可能となります。資産承継の観点からも、将来世代に負動産を残さないよう計画を立てておくことが望ましいでしょう。
まとめ ~長期的視点に立った資産運用の重要性~
「2025年問題」に端を発したサブリース契約の収益悪化リスクは、少子高齢化という日本社会の構造的問題に起因するため、完全にその影響を避けることは難しい面があります。しかし、不動産オーナーの側でできる工夫や対策によって、その影響度合いを緩和し、たとえ厳しい市場環境になっても収益を維持できる可能性は充分にあります。大切なのは短期的な楽観や悲観に振り回されず、長期的な視野を持って資産価値を守り育てる姿勢です。人口や社会の変化は緩やかでも着実に進行していきます。不動産賃貸業もまた時代とともに戦略をアップデートし続ける必要があります。将来を見据えたリスクシナリオを描き、早め早めに手を打ちながら、腰を据えた資産運用を行うことがこれからの不動産オーナーには求められます。そのためにも、本記事で述べたようなポイントを参考に、来たる2025年以降も安定した賃貸経営を継続できるよう備えておきましょう。長期的視点に立った堅実な経営こそが、大きな環境変化の時代における最善のリスクヘッジと言えるのです。

稲澤大輔
INA&Associates株式会社 代表取締役。大阪・東京・神奈川を拠点に、不動産売買・賃貸仲介・管理を手掛ける。不動産業界での豊富な経験をもとに、サービスを提供。 「企業の最も重要な資産は人財である」という理念のもと、人財育成を重視。持続可能な企業価値の創造に挑戦し続ける。 【取得資格(合格資格含む)】 宅地建物取引士、行政書士、個人情報保護士、マンション管理士、管理業務主任者、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、賃貸不動産経営管理士、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者、不動産コンサルティングマスター

.png)