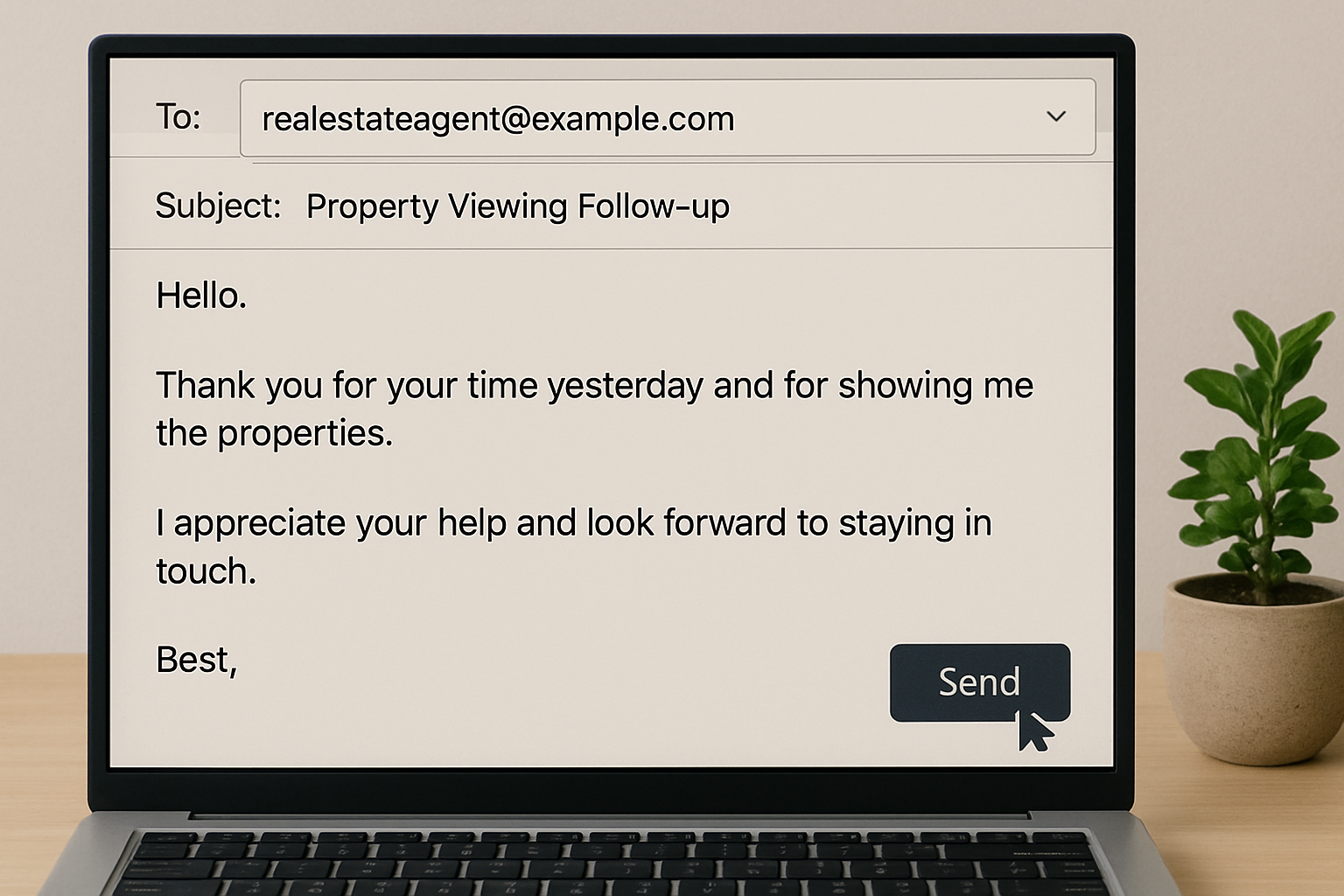近年、不動産投資の世界において、投資家自身が宅建業免許を取得するケースが増加しています。「レインズが使える」「物件情報が集まりやすい」「仲介手数料収入が得られる」といった様々なメリットを耳にして、自身も宅建業者になることを検討している投資家の方も多いのではないでしょうか。
しかし、宅建業免許の取得には相応の費用と時間、そして継続的な義務が伴います。果たして、不動産投資家にとって宅建業者になることは本当にメリットが多いのでしょうか。
本記事では、INA&Associates株式会社として長年不動産業界に携わってきた経験をもとに、不動産投資家が宅建業者になることの具体的なメリットとデメリット、そして費用対効果について詳しく解説いたします。これから宅建業免許の取得を検討されている投資家の皆様にとって、判断材料となる情報を提供できれば幸いです。
宅建業者と不動産投資家の違いを理解する
宅建業免許取得のメリットを論じる前に、まず宅建業者と不動産投資家の根本的な違いを明確にしておく必要があります。
不動産投資家の定義と活動内容
不動産投資家とは、主に物件の購入・保有・売却・賃貸を通じて収益を得る個人または法人を指します。その活動の特徴は以下の通りです。
不動産投資家の主な活動は、自己資金や融資を活用して収益物件を取得し、賃料収入や売却益を得ることです。多くの場合、長期保有による賃貸経営を基本戦略とし、安定したキャッシュフローの構築を目指します。また、市場動向を見極めながら適切なタイミングで物件を売却し、キャピタルゲインを獲得することも重要な収益源となります。
投資家の活動は基本的に自己の資産運用として行われるため、他人の不動産取引に関与することはありません。そのため、多くの場合において宅建業免許は必要とされていないのが現状です。
宅建業者の定義と業務範囲
一方、宅建業者とは、宅地建物取引業法(宅建業法)に基づき、反復継続して不動産の売買・交換・仲介・代理を行う事業者を指します。宅建業者として認められるためには、国土交通省または都道府県知事の免許取得が必須となります。
宅建業者の業務範囲は多岐にわたります。不動産の売買仲介では、売主と買主の間に立って契約成立をサポートし、法定の仲介手数料を受領します。賃貸仲介においても同様に、貸主と借主の橋渡し役を担います。また、自ら不動産を取得して販売する売主業務や、他人の依頼を受けて不動産取引を代理する業務も行います。
これらの業務を適切に遂行するため、宅建業者には宅建士の設置義務や重要事項説明の実施義務など、厳格な法的要件が課せられています。
両者の関係性と重複する領域
不動産投資家と宅建業者は、一見すると異なる領域で活動しているように見えますが、実際には重複する部分が存在します。
特に、短期間での物件転売を繰り返す投資手法を採用する場合、その活動が宅建業に該当する可能性があります。法律上、営利目的で反復継続的に不動産売買を行う行為は宅建業とみなされるため、このような投資スタイルを取る場合は宅建業免許の取得が必要となります。
また、投資家が自身の知識や経験を活かして他人の不動産取引をサポートし、対価を受け取る場合も宅建業に該当します。このような活動を行う際は、適切な免許を取得していなければ宅建業法違反となるリスクがあります。
このように、不動産投資家と宅建業者の境界線は必ずしも明確ではなく、投資家の活動内容によっては宅建業免許の取得が必要となるケースも存在するのです。
不動産投資家が宅建業者になる5つの主要メリット
不動産投資家が宅建業免許を取得することで得られるメリットは多岐にわたります。ここでは、特に重要な5つのメリットについて詳しく解説いたします。
メリット1:レインズ(REINS)へのアクセスによる情報優位性
宅建業免許を取得する最大のメリットの一つが、レインズ(RealEstateInformationNetworkSystem)へのアクセス権限を得られることです。
レインズは、全国の宅建業者が物件情報を共有するためのオンラインシステムです。このシステムには、一般の不動産ポータルサイトには掲載されていない物件情報や、詳細な取引事例データが蓄積されています。宅建業者のみがアクセス可能なこのシステムを利用することで、投資家は以下のような情報優位性を獲得できます。
まず、未公開物件情報への早期アクセスが可能になります。優良な投資物件は市場に出る前に宅建業者間で取引されることが多く、一般投資家がこれらの情報を入手する頃には既に売却済みとなっているケースが少なくありません。レインズへのアクセス権限を持つことで、このような優良物件をいち早く発見し、投資機会を逃すリスクを大幅に軽減できます。
次に、正確な市場相場の把握が可能になります。レインズには過去の取引事例が詳細に記録されており、類似物件の成約価格や市場動向を正確に分析できます。この情報は投資判断において極めて重要であり、適正な購入価格の設定や将来の収益予測の精度向上に直結します。
さらに、競合他社の動向把握も可能になります。どのような物件がどの程度の期間で成約しているか、価格設定の傾向はどうかといった市場の動きを詳細に分析することで、より戦略的な投資活動を展開できます。
メリット2:仲介手数料収入による収益源の多様化
宅建業免許を取得することで、従来の賃料収入や売却益に加えて、仲介手数料収入という新たな収益源を獲得できます。
不動産の売買仲介における手数料は、宅建業法により上限が定められています。売買価格が400万円を超える場合、「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限となります。例えば、3,000万円の物件の売買仲介を行った場合、最大で105.6万円(税込)の仲介手数料を受領できます。
この仲介手数料収入の魅力は、比較的短期間で確実な収益を得られることです。賃貸経営では長期間にわたって賃料収入を得る必要がありますが、仲介業務では契約成立と同時に手数料収入を獲得できます。また、自己資金を物件取得に投入する必要がないため、資金効率の向上も期待できます。
さらに、投資家としての経験と知識を活かすことで、付加価値の高いサービスを提供できます。単なる物件紹介にとどまらず、投資収益性の分析や将来の市場予測など、専門的なアドバイスを提供することで、他社との差別化を図り、より高い手数料収入を獲得することも可能です。
メリット3:重要事項説明書の深い理解による投資判断力向上
宅建業者として活動することで、重要事項説明書の内容を深く理解できるようになります。これは投資家としての判断力向上に大きく寄与します。
重要事項説明書は、不動産取引において買主が知っておくべき重要な事項をまとめた書面です。物件の権利関係、法的制限、インフラ整備状況、周辺環境など、投資判断に直結する情報が詳細に記載されています。
多くの投資家は、重要事項説明を受ける際に内容を十分に理解できずに契約を進めてしまうケースがあります。しかし、宅建業者として重要事項説明を行う立場になることで、各項目の意味や投資への影響を深く理解できるようになります。
例えば、都市計画法上の制限や建築基準法上の制限は、将来の建て替えや増改築の可能性に大きく影響します。また、インフラ整備の状況は維持管理費用に直結し、周辺環境の変化予測は賃料設定や空室リスクの評価に重要な要素となります。
このような専門知識を身につけることで、リスクの早期発見や収益性の正確な評価が可能になり、より質の高い投資判断を行えるようになります。
メリット4:法律知識の習得によるリスク回避能力強化
宅建業免許を取得するためには、宅建業法をはじめとする不動産関連法規の知識習得が必要です。この法律知識は、投資活動におけるリスク回避能力の大幅な向上をもたらします。
不動産投資には様々な法的リスクが潜んでいます。契約不適合責任、瑕疵担保責任、借地借家法上の制限、税法上の取扱いなど、知識不足により思わぬ損失を被るケースは少なくありません。
宅建士として必要な法律知識を身につけることで、契約書の内容を正確に理解し、不利な条項や潜在的なリスクを事前に発見できるようになります。また、適切な契約条件の交渉も可能になり、より有利な取引条件で物件を取得できる可能性が高まります。
さらに、法律改正や制度変更に関する情報も継続的に入手できるため、法的環境の変化に迅速に対応することが可能です。これにより、新たな規制による影響を最小限に抑え、場合によっては制度変更を投資機会として活用することもできます。
メリット5:業界内での信頼度向上とネットワーク拡大
宅建業免許を取得することで、不動産業界内での信頼度が大幅に向上します。これは、新たなビジネス機会の創出や有益な情報の入手につながる重要なメリットです。
宅建業者として認められることで、他の不動産会社や金融機関、建設会社などとの対等なビジネス関係を構築できます。単なる顧客としてではなく、同業者として扱われることで、より深いレベルでの情報交換や協業が可能になります。
また、宅建協会や不動産協会などの業界団体への参加も可能になります。これらの団体では定期的に研修会や情報交換会が開催されており、最新の市場動向や法改正情報、成功事例などを学ぶ機会が豊富に提供されています。
さらに、金融機関からの信頼度向上も期待できます。宅建業者として事業を行っていることは、不動産に関する専門知識と経験を有している証明となり、融資審査において有利に働く可能性があります。特に事業性融資を検討する際には、この信頼度の向上が大きなメリットとなります。
業界内でのネットワーク拡大により、優良物件情報の早期入手や有利な条件での取引機会も増加します。信頼関係に基づく情報提供は、一般的な営業活動では得られない貴重な投資機会をもたらすことが多く、長期的な投資成果の向上に大きく寄与します。
宅建業免許取得に必要な条件と費用
宅建業免許取得のメリットを理解したところで、実際に免許を取得するために必要な条件と費用について詳しく見ていきましょう。
宅建士資格の取得
宅建業免許を取得するためには、まず宅建士資格を取得する必要があります。宅建業法では、営業所ごとに従業員5人に対して1人以上の宅建士を設置することが義務付けられています。
宅建士試験は年に一度、例年10月の第3日曜日に実施されます。受験資格に制限はなく、学歴や年齢、実務経験に関係なく誰でも受験可能です。試験はマークシート形式で実施され、合格率は例年15%前後となっています。
試験に合格した後は、2年以上の実務経験または登録実務講習の修了が必要です。実務経験がない場合は、指定機関が実施する登録実務講習(約1ヶ月間)を受講することで要件を満たすことができます。その後、宅建士証の交付を申請し、受け取ることで宅建士として活動を始められます。
事務所の設置要件
宅建業を営むためには、適切な事務所を設置する必要があります。事務所には以下の要件が定められています。
事務所は継続的に業務を行うことができる施設である必要があります。住宅の一部を事務所として使用することも可能ですが、業務に支障がない独立した空間を確保する必要があります。また、事務所には宅建業者票の掲示、報酬額表の掲示、帳簿の備え付けなどが義務付けられています。
さらに、事務所には専任の宅建士を設置する必要があります。
保証協会への加入
宅建業者は、取引の安全を確保するために営業保証金の供託または保証協会への加入が義務付けられています。
営業保証金を供託する場合、主たる営業所について1,000万円、その他の営業所について1箇所につき500万円を法務局に供託する必要があります。一方、保証協会に加入する場合は、主たる営業所について60万円、その他の営業所について1箇所につき30万円の弁済業務保証金分担金を納付します。
多くの宅建業者は、資金負担を軽減するために保証協会への加入を選択しています。保証協会には全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)と全日本不動産協会(全日)があり、それぞれ異なるサービスや特典を提供しています。
取得費用の詳細
宅建業免許取得に必要な費用を以下の表にまとめました。
| 項目 | 知事免許 | 大臣免許 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 免許申請手数料 | 33,000円 | 90,000円 | 法定費用 |
| 保証協会入会金 | 約250,000円 | 約250,000円 | 全宅連の場合 |
| 弁済業務保証金分担金 | 600,000円 | 600,000円 | 主たる営業所のみの場合 |
| 宅建士登録費用 | 37,000円 | 37,000円 | 登録手数料 |
| 宅建士証交付費用 | 4,500円 | 4,500円 | 証明書発行手数料 |
| 登録実務講習費用 | 約20,000円 | 約20,000円 | 実務経験がない場合 |
| 事務所設置費用 | 100,000円~ | 100,000円~ | 賃料・設備費等 |
| 合計 | 約1,044,500円~ | 約1,101,500円~ | 初年度概算 |
この表に示した費用は初年度の概算であり、実際の費用は地域や選択する保証協会、事務所の条件などによって変動します。また、免許取得後も年会費や更新費用などの継続的な費用が発生することも考慮する必要があります。
免許取得までの期間
宅建業免許の取得には相応の期間が必要です。都道府県知事免許の場合、申請から免許交付まで約30~40日程度を要します。国土交通大臣免許の場合は、約3~4ヶ月程度の期間が必要となります。
さらに、保証協会への加入手続きも含めると、実際に営業を開始できるまでには知事免許で約60日、大臣免許で約4~5ヶ月程度の期間を見込んでおく必要があります。
宅建士資格を持っていない場合は、試験の受験から始める必要があるため、さらに長期間を要することになります。年1回の試験であることを考慮すると、計画的な準備が重要となります。
デメリットと注意点も理解しておく
宅建業免許取得には多くのメリットがある一方で、デメリットや注意点も存在します。適切な判断を行うために、これらの点についても十分に理解しておく必要があります。
宅建業法による規制の強化
宅建業者になることで、宅建業法による厳格な規制を受けることになります。これは業務の自由度に一定の制限をもたらします。
まず、広告規制があります。宅建業者は不動産の広告において、誇大広告や誤認を招く表現を使用することが禁止されています。また、開発許可前の物件や建築確認前の物件については、広告自体が制限される場合があります。これらの規制により、マーケティング活動において慎重な対応が求められます。
次に、契約書面の作成義務があります。宅建業者は売買契約や賃貸借契約において、法定の契約書面を作成し、買主や借主に交付する義務があります。また、重要事項説明書の作成と説明も必須となり、これらの業務には専門知識と相応の時間を要します。
さらに、クーリングオフ制度への対応も必要です。宅建業者が売主となる場合、買主は一定の条件下で契約を解除できる権利を有します。このような消費者保護規定により、契約後であってもリスクが残存する可能性があります。
維持費用の継続的負担
宅建業免許を維持するためには、継続的な費用負担が発生します。
保証協会の年会費は、協会や地域によって異なりますが、年間数万円から十数万円程度が一般的です。また、宅建業免許は5年ごとの更新が必要であり、更新時には再度手数料の支払いが必要となります。
事務所の維持費用も継続的に発生します。賃料、光熱費、通信費などの基本的な運営費用に加えて、宅建業者として必要な設備や備品の維持管理費用も考慮する必要があります。
これらの維持費用は、宅建業としての収益が十分でない場合、投資家としての収益を圧迫する要因となる可能性があります。
法定講習の義務
宅建士は5年ごとの法定講習を受講する義務があります。この講習は宅建士証の有効期間更新のために必要であり、受講しない場合は宅建士として活動できなくなります。
法定講習は通常1日間の日程で実施され、受講料として1万円程度の費用が発生します。また、講習会場への交通費や、講習受講のための時間的コストも考慮する必要があります。
さらに、宅建業法や関連法規の改正に対応するため、継続的な学習も必要となります。これらの学習コストは、時間的・金銭的な負担として考慮すべき要素です。
業務範囲の制限
宅建業者として活動する場合、業務範囲に一定の制限が生じる可能性があります。
例えば、宅建業者が自ら売主となって不動産を販売する場合、瑕疵担保責任や契約不適合責任を負うことになります。これらの責任は、単純な投資家として活動する場合よりも重い責任となる可能性があります。
また、宅建業者として他人の不動産取引に関与する場合、善管注意義務や忠実義務を負うことになります。これらの義務に違反した場合、損害賠償責任を負うリスクがあります。
税務上の取扱いの変化
宅建業者として事業を行う場合、税務上の取扱いが変化する可能性があります。
不動産投資家として活動する場合は不動産所得として申告しますが、宅建業者として活動する場合は事業所得として申告する必要があります。これにより、経費の計上方法や税率が変化する可能性があります。
また、消費税の課税事業者となる可能性も高くなります。年間売上高が1,000万円を超える場合は消費税の納税義務が生じ、税務処理が複雑になります。
これらの税務上の変化は、必ずしもデメリットとは限りませんが、適切な税務処理を行うための知識習得や税理士への相談費用などが必要となる場合があります。
宅建業免許が必要なケースと不要なケース
不動産投資家が宅建業免許の取得を検討する際、自身の投資活動が宅建業に該当するかどうかを正確に判断することが重要です。ここでは、具体的なケースを挙げながら説明いたします。
免許が必要となる具体的な業務
宅建業法では、以下のような活動を宅建業として定義しており、これらを業として行う場合は免許が必要となります。
短期間での反復継続的な売買
営利目的で反復継続的に不動産の売買を行う場合は、宅建業に該当します。具体的には、以下のようなケースが該当する可能性があります。
1年以内に複数の物件を購入し、リフォームやリノベーションを施した後に売却する活動を継続的に行う場合、これは宅建業とみなされる可能性が高くなります。特に、購入時点で売却を前提としている場合や、短期間での転売を主たる収益源としている場合は注意が必要です。
法人が不動産を仕入れ、継続的に販売している場合は、個人よりも宅建業として認定されやすい傾向があります。ただし、個人であっても反復継続性が認められる場合は宅建業に該当する可能性があります。
他人の不動産取引の仲介・代理
他人の不動産売買や賃貸借の仲介・代理を行い、報酬を受け取る場合は、明確に宅建業に該当します。
例えば、不動産投資家が自身の知識や経験を活かして、知人や顧客の不動産売買をサポートし、成功報酬や手数料を受け取る場合は宅建業免許が必要です。また、自身が所有する物件の入居者募集を他人に依頼され、報酬を受け取る場合も同様です。
不動産特定共同事業
複数の投資家から資金を集めて不動産投資を行い、収益を分配する事業を行う場合は、不動産特定共同事業法の許可に加えて、宅建業免許も必要となる場合があります。
免許なしで可能な不動産投資活動
一方、以下のような活動は宅建業に該当せず、免許なしで行うことができます。
長期保有による賃貸経営
自己所有物件を長期間保有し、賃料収入を得る活動は宅建業には該当しません。これは最も一般的な不動産投資の形態であり、多くの投資家がこの方法で資産形成を行っています。
アパートやマンションを購入し、入居者に賃貸して家賃収入を得る行為は、不動産の「賃貸」であり、宅建業法の規制対象である「売買・交換・仲介・代理」には該当しません。
自己所有物件の売却
自己の資産として保有していた不動産を売却する行為は、反復継続性がない限り宅建業には該当しません。
数年に1回程度の頻度で所有物件を売却し、キャピタルゲインを得る行為は、一般的な資産運用の範囲内とみなされます。ただし、短期間での転売を繰り返す場合は反復継続性が認められ、宅建業に該当する可能性があります。
自己管理による不動産管理
自己所有物件の管理業務は宅建業には該当しません。入居者との賃貸借契約の締結、家賃の集金、建物の維持管理などは、所有者として当然の権利・義務の範囲内とみなされます。
ただし、他人が所有する物件の管理を業として請け負う場合は、賃貸不動産管理業の登録が必要となる場合があります。
グレーゾーンの判断基準
実際の投資活動においては、宅建業に該当するかどうかの判断が困難なケースも存在します。以下のような要素が判断の基準となります。
反復継続性の判断
反復継続性は、宅建業該当性を判断する最も重要な要素の一つです。しかし、何回以上の取引で反復継続性が認められるかについては、明確な基準は示されていません。
一般的には、年間2~3回以上の売買を継続的に行う場合は注意が必要とされています。ただし、取引の規模や期間、動機なども総合的に考慮されるため、個別のケースごとに慎重な判断が必要です。
営利目的の判断
営利目的の有無も重要な判断要素です。相続により取得した不動産を処分する場合や、生活環境の変化により住み替えを行う場合など、営利以外の目的での売却は宅建業には該当しません。
一方、購入時点で転売による利益獲得を目的としている場合や、事業として不動産売買を行っている場合は営利目的と判断される可能性が高くなります。
業としての実態
業としての実態があるかどうかも判断要素となります。継続的に事務所を構えて不動産売買を行っている場合や、広告宣伝を行って顧客を募集している場合は、業としての実態があると判断される可能性があります。
これらの判断基準は複合的に考慮されるため、グレーゾーンに該当する可能性がある場合は、事前に専門家に相談することをお勧めいたします。宅建業法違反は刑事罰の対象となる場合もあるため、慎重な対応が必要です。
まとめ:費用対効果を慎重に検討して判断を
不動産投資家が宅建業者になることには、確かに多くのメリットが存在します。本記事で解説した5つの主要メリットを改めて整理すると以下の通りです。
レインズへのアクセスにより、一般には公開されていない優良物件情報を早期に入手でき、投資機会の拡大が期待できます。仲介手数料収入という新たな収益源の獲得により、収益の多様化と資金効率の向上が可能になります。重要事項説明書の深い理解により、投資判断の精度が向上し、リスク回避能力が強化されます。法律知識の習得により、契約内容の適切な理解と有利な条件での交渉が可能になります。そして、業界内での信頼度向上とネットワーク拡大により、長期的な投資成果の向上が期待できます。
しかし、これらのメリットを享受するためには、初期費用として約100万円以上の投資が必要であり、継続的な維持費用や法的義務も伴います。また、宅建業法による規制を受けることで、業務の自由度に一定の制限が生じる可能性もあります。
投資スタイルに応じた判断基準
宅建業免許取得の判断は、個々の投資家の投資スタイルや事業規模によって大きく異なります。
積極的な事業拡大を目指す投資家にとって、宅建業免許は強力なツールとなり得ます。特に、年間の不動産取引額が数億円規模に達する場合や、複数の収益源を確保したい場合は、免許取得のメリットが費用を上回る可能性が高いでしょう。
一方、小規模な投資活動を行う投資家や長期保有を基本戦略とする投資家にとっては、免許取得の費用対効果は限定的かもしれません。このような場合は、信頼できる宅建業者とのパートナーシップを構築することで、免許取得と同様の効果を得られる可能性があります。
次のアクション提示
宅建業免許取得を検討されている投資家の皆様には、以下のステップでの検討をお勧めいたします。
まず、現在の投資活動の規模と将来の事業計画を明確にしてください。年間の取引額、取引頻度、事業拡大の方向性などを具体的に数値化することで、免許取得の必要性をより客観的に判断できます。
次に、費用対効果の詳細な分析を行ってください。初期費用と維持費用を正確に算出し、期待される収益増加額と比較検討することが重要です。
そして、専門家への相談を行うことをお勧めいたします。宅建業法の解釈や税務上の取扱いなど、専門的な判断が必要な事項については、行政書士や税理士などの専門家のアドバイスを求めることが賢明です。
よくある質問(FAQ)
Q1:宅建業免許の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
A:都道府県知事免許の場合、申請から免許交付まで約30~40日程度を要します。国土交通大臣免許の場合は約3~4ヶ月程度が必要です。ただし、宅建士資格を持っていない場合は、まず宅建士試験に合格する必要があるため、年1回の試験スケジュールを考慮すると、さらに長期間を要することになります。保証協会への加入手続きも含めると、実際の営業開始まで知事免許で約2ヶ月、大臣免許で約4~5ヶ月程度を見込んでおく必要があります。
Q2:個人でも宅建業免許を取得できますか?
A:はい、個人でも宅建業免許を取得することは可能です。ただし、個人の場合でも法人と同様の要件を満たす必要があります。具体的には、宅建士資格の取得、適切な事務所の設置、営業保証金の供託または保証協会への加入などが必要です。また、個人事業主として宅建業を営む場合は、事業所得として確定申告を行う必要があります。
Q3:宅建業免許を取得すると税務上のメリットはありますか?
A:宅建業免許取得により税務上の取扱いが変化する可能性があります。不動産所得から事業所得への変更により、経費の計上範囲が拡大する場合があります。また、青色申告特別控除の適用や、事業用資産の減価償却など、税務上有利な取扱いを受けられる可能性があります。ただし、消費税の課税事業者となる可能性も高くなるため、総合的な検討が必要です。詳細については税理士にご相談されることをお勧めいたします。
Q4:レインズの利用料金はいくらですか?
A:レインズの利用料金は、加入する保証協会の会費に含まれており、別途利用料金を支払う必要はありません。全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)や全日本不動産協会(全日)などの保証協会に加入することで、レインズを無料で利用できます。ただし、保証協会の年会費として数万円から十数万円程度の費用が継続的に発生します。
Q5:宅建業免許を取得せずに不動産投資を続けるリスクはありますか?
A:宅建業に該当する活動を免許なしで行った場合、宅建業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、無免許営業により得た報酬の返還を求められる場合もあります。一方、長期保有による賃貸経営や、反復継続性のない自己所有物件の売却など、宅建業に該当しない投資活動であれば、免許なしでも法的問題はありません。重要なのは、自身の投資活動が宅建業に該当するかどうかを正確に判断することです。

稲澤大輔
INA&Associates株式会社 代表取締役。大阪・東京・神奈川を拠点に、不動産売買・賃貸仲介・管理を手掛ける。不動産業界での豊富な経験をもとに、サービスを提供。 「企業の最も重要な資産は人財である」という理念のもと、人財育成を重視。持続可能な企業価値の創造に挑戦し続ける。 【取得資格(合格資格含む)】 宅地建物取引士、行政書士、個人情報保護士、マンション管理士、管理業務主任者、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、賃貸不動産経営管理士、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者、不動産コンサルティングマスター

.png)