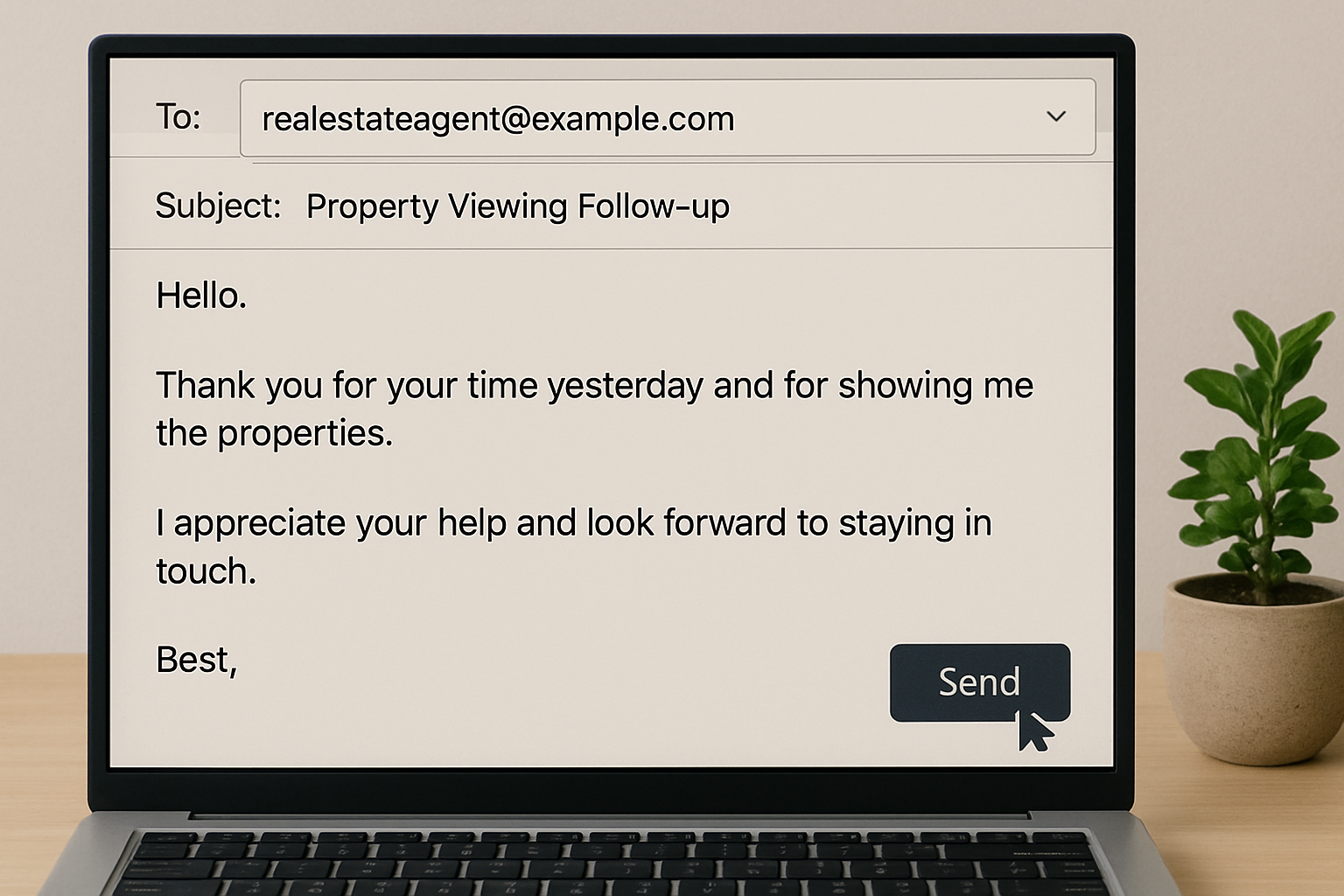不動産投資は、資産形成の有効な手段として近年ますます注目を集めています。特に富裕層の個人投資家にとって、不動産投資は資産形成や節税対策、相続対策など様々な目的で選ばれている投資手法です。安定した賃料収入(インカムゲイン)と資産価値の上昇による売却益(キャピタルゲイン)の両方を得られる可能性があり、さらにインフレへの耐性やリスクヘッジ効果も期待できます。本記事では、多くの人が不動産投資を選ぶ具体的な理由について、以下の観点から詳しく解説いたします。
資産形成に不動産投資が有効な理由
不動産投資は他の投資手法と比較して、長期的な資産形成において安定した利回りが期待できるとされています。株式投資やFXのようなハイリスク・ハイリターン商品に比べると価格変動が小さく、経済状況に左右されにくい実物資産であるため、時間をかけて着実に資産を増やすことが可能です。一方で、預金や債券といったローリスク・ローリターンの手法に比べれば利回りは高く、インフレ対策としても有効な点で資産形成に有利な投資先と言えます。
また、不動産投資は金融機関から融資を受けて始められるケースが多く、レバレッジ(てこの原理)を利かせられるのも大きな魅力です。少ない自己資金でも銀行ローンを活用することで、より高額の不動産を取得して運用益を得ることができます。借入を活用して不動産を購入し、長期にわたり賃貸収入でローンを返済していく仕組みは、一種の強制貯蓄効果をもたらし、着実な資産形成につながります。実際、投資用不動産を長期保有すれば、たとえ市場価格が一時的に下落しても毎月の家賃収入でカバーできるため、最終的に利益が出る可能性が高まるとされています。長期運用によって不動産に「働いてもらう」ことで、継続的な資産拡大が期待できるのです。
節税対策としての不動産投資の仕組みと効果
不動産投資は節税の面でも効果を発揮します。日本の税制では、不動産賃貸による所得が赤字(経費が収入を上回る状態)になった場合、その赤字分を他の所得と相殺できる「損益通算」の仕組みがあります。例えば、不動産の減価償却費やローン金利などを経費計上した結果、賃貸経営上は赤字となれば、その分を給与所得などから差し引いて所得税を減額できるのです。高額所得者ほど税率が高いため、この節税効果のメリットは大きく、賃貸収入と合わせて手取りベースでの利回り向上につながります。
さらに、不動産投資による節税効果は所得税だけに留まりません。物件購入時には登録免許税や不動産取得税の軽減措置が受けられる場合があるほか、保有中も固定資産税の特例措置が適用できることがあります。特に新築物件や一定の要件を満たす住宅用物件では、固定資産税の減額措置が数年間適用されるケースもあり、中長期的なコスト削減に寄与します。また、将来的に物件を売却する際も、長期保有することで不動産の譲渡所得税率が優遇される(短期より長期の方が税率が低い)ため、売却益に対する税負担を抑えることができます。これらの仕組みにより、不動産投資は総合的な節税対策として機能し、投資リターンを高める一助となっています。
安定したインカムゲインとキャピタルゲインのバランス
不動産投資が人気を集める大きな理由の一つに、安定したインカムゲインと将来的なキャピタルゲインという二つのリターンをバランス良く狙える点があります。賃貸物件の家賃収入による利益はインカムゲインと呼ばれ、物件を保有している間は毎月定期的に得られる安定収入です。一方、物件売却時に購入時より高く売れた場合の差益はキャピタルゲインと呼ばれ、不動産売買による一時的な利益となります。不動産投資では、このインカムゲインとキャピタルゲインの“二刀流”で収益を得ることが可能であり、ここに他の金融商品にはない魅力があります。
まずインカムゲインの安定性ですが、不動産の家賃収入は景気の影響を受けにくく、大幅に減額されたり突然ゼロになるケースは稀です。にもあるように、株式の配当金と異なり家賃が急激に下落することは考えづらく、一棟マンションやアパートなら入居者全員が一度に退去するような事態も起こりにくいため、将来の収入を予測しやすいというメリットがあります。この安定したインカムゲインにより、ローンの返済や維持管理費をまかないつつ、手元に毎月一定の現金収入を得て生活や事業の安定化に役立てることができます。
一方のキャピタルゲインについても、不動産市況や物件の希少性によっては大きな利益を生む可能性があります。特に土地神話の強い日本においては、好立地の不動産を長期間保有することで取得時より高値で売却できるケースも少なくありません。もちろん不動産価格は景気や需給により変動しますが、インカムゲインを得ながらタイミングを見計らって売却益を狙うといった柔軟な戦略が取れるのは不動産投資ならではです。実際、多くの投資家は売却によるキャピタルゲインを最終目標としつつ、売却までの期間は賃貸運用でインカムゲインを稼ぐという二段構えの運用を行っています。このように、定常的な収入と資産価値の上昇という両面からリターンを追求できる点が、不動産投資が選ばれる大きな理由です。
富裕層が好む資産分散手法としての不動産の役割
富裕層の投資家が資産運用で重視する戦略の一つに「分散投資」があります。資産を株式、債券、現金、不動産といった異なる資産クラスに振り分けることで、一部の資産が値下がりしても他でカバーし、全体として資産を堅実に増やす狙いがあります。実際、純資産数億円規模の富裕層では、一つの資産だけに集中投資するケースは少なく、不動産も重要なポートフォリオの一部として位置付けられています。ある調査では、世界の超富裕層(純資産30億円超)の資産配分に占める不動産投資の割合は平均14.6%にも上ると報告されています。日本の富裕層は特に不動産への比重が高い傾向があるとも言われており、不動産が資産防衛と分散において重要視されていることがうかがえます。
不動産が資産分散に果たす役割として注目すべきは、その値動きの特性です。前述の通り不動産価格は株式市場ほど日々乱高下せず、景気変動による影響は緩やかです。株式や為替が下落局面にあっても不動産が直ちに同調して下落するとは限らず、むしろ長期的には独自のサイクルで価値を推移します。そのため、株式中心のポートフォリオに不動産という異なる値動きをする資産を組み入れることで、全体のボラティリティ(変動リスク)を下げ、安定した運用成績を得やすくなります。実際に金融資産1億円以上の富裕層投資家の約86%が、不動産だけでなく株式や債券など複数の資産に分散投資を実践しているとの調査結果もあります。このように、不動産は富裕層に好まれる資産分散手法の一つであり、ポートフォリオの安定性向上とリスク分散に寄与する重要な役割を担っています。
インフレ対策・リスクヘッジ資産としての不動産の魅力
不動産は「インフレに強い資産」「有事のリスクヘッジ手段」としても高く評価されています。一般に、インフレーション(物価上昇)が進行すると現預金などの金融資産の価値は目減りしてしまいますが、不動産のような実物資産は物価上昇局面でも価値が下がりにくいとされています。実際、景気が加熱して物価(消費者物価指数)が上昇する局面では、不動産価格や賃料もそれに応じて上昇する傾向が歴史的にも確認されています。例えば過去の日本や米国の高インフレ期においては、住宅価格と物価の相関性が高く推移し、不動産が優れたインフレヘッジの効果を発揮したことが示されています。このため、インフレリスクへの備えとして、多くの富裕層・投資家がポートフォリオに不動産などの実物資産を組み入れているのです。
加えて、不動産はリスクヘッジの観点でも心強い資産です。株式市場が企業業績や世界情勢の影響で急落するような場合でも、不動産価格が一夜にして大暴落する可能性は極めて低く、日々の価格変動がマイルドです。たとえば大きな経済ショックや企業不祥事が報道されても株価ほど瞬間的に反応することはなく、賃貸不動産であれば毎月の家賃収入がすぐになくなるわけでもありません。むしろ不動産は「守りの資産」として、景気後退時にも一定の価値と収益を生み続ける点が魅力と言えます。また、地価や賃料がインフレに連動して上昇する局面では、その保有資産価値が実質的に目減りしないどころか資産全体の価値向上にもつながり得ます。このように、不動産を保有することはインフレから資産を守り、市場変動リスクを緩和する一種のリスクヘッジとなります。長期的な視点で見れば、現金を大量に保有し続けるよりも不動産など実物資産に置き換えておく方が資産保全に有効だと、多くの投資家が認識しています。
相続対策・事業承継対策としての不動産活用
不動産は次世代への財産継承においても有用なツールとなります。相続対策の観点では、現金や上場株式が相続評価額において100%時価評価されるのに対し、不動産は路線価や固定資産税評価額を基準とするため実勢価格より低く評価される特性があります。
事業オーナーの立場においても、不動産は事業承継対策として活用できます。自社株の評価額や事業用資産の評価が高いと、後継者への株式譲渡や相続の際に多額の相続税・贈与税負担が生じる恐れがあります。そこで、事業承継に先立って法人や個人が不動産を購入し資産構成に組み込んでおくと、資産全体の評価額を引き下げる効果が期待できます。前述の土地の路線価評価の仕組みを法人資産にも応用するイメージで、現預金を不動産に置き換えることで企業オーナーの株式評価額(純資産評価)が下がり、結果として承継時の税負担を軽減できる場合があります。さらに、一定の要件を満たせば適用できる「小規模宅地等の特例」という制度もあります。これは事業用や居住用の土地を相続する際に、その評価額を50〜80%減額できる優遇制度で、多くの資産を保有する富裕層ほど積極的に活用を検討する価値があります。例えば事前に賃貸用不動産として活用しておけば、相続発生時にその土地が貸付事業用宅地等として特例適用され、大幅な節税効果を得ることも可能です。
このように、不動産は将来の相続や事業承継に備える手段として非常に有効です。生前に不動産へ資産シフトしておくことで、遺された家族に現物資産として残せるだけでなく、相続税評価額を抑えて円滑に財産を承継できます。実際に不動産投資を行う富裕層の中には、資産保全と次世代へのスムーズな引き渡しを見据えて物件を購入する方も少なくありません。相続・承継は専門的な知識を要する分野ですが、不動産を上手に組み入れることで税負担とリスクをコントロールし、大切な財産を守りながら次世代に引き継ぐことが可能になるのです。
おわりに
以上のように、不動産投資が選ばれる理由としては、資産形成における有効性、節税メリット、インカムゲインとキャピタルゲインの両取り、資産分散効果、インフレ対策・リスクヘッジ機能、そして相続・事業承継対策での有用性と多岐にわたります。それぞれの項目で述べたように、不動産投資は単なる利益追求だけでなく、資産を守り育て次世代へ繋ぐ包括的な手段として機能しうる点に大きな魅力があります。超富裕層の方々に限らず、将来を見据えて資産ポートフォリオを構築するうえで、不動産を組み入れる意義は十分に高いと言えるでしょう。
もちろん、不動産投資には物件の流動性や管理の手間、経営リスクなど留意すべき点も存在します。しかし、適切な物件選定と専門家の助言を得て運用すれば、そのリスクは十分コントロール可能です。長期的視野に立ち、堅実かつ分散の利いた資産運用を目指す上で、不動産投資は有力な選択肢となり得ます。資産規模や運用目的に合わせて、不動産の持つ多面的なメリットを最大限に活用していただきたいと思います。

稲澤大輔
INA&Associates株式会社 代表取締役。大阪・東京・神奈川を拠点に、不動産売買・賃貸仲介・管理を手掛ける。不動産業界での豊富な経験をもとに、サービスを提供。 「企業の最も重要な資産は人財である」という理念のもと、人財育成を重視。持続可能な企業価値の創造に挑戦し続ける。 【取得資格(合格資格含む)】 宅地建物取引士、行政書士、個人情報保護士、マンション管理士、管理業務主任者、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、賃貸不動産経営管理士、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者、不動産コンサルティングマスター

.png)