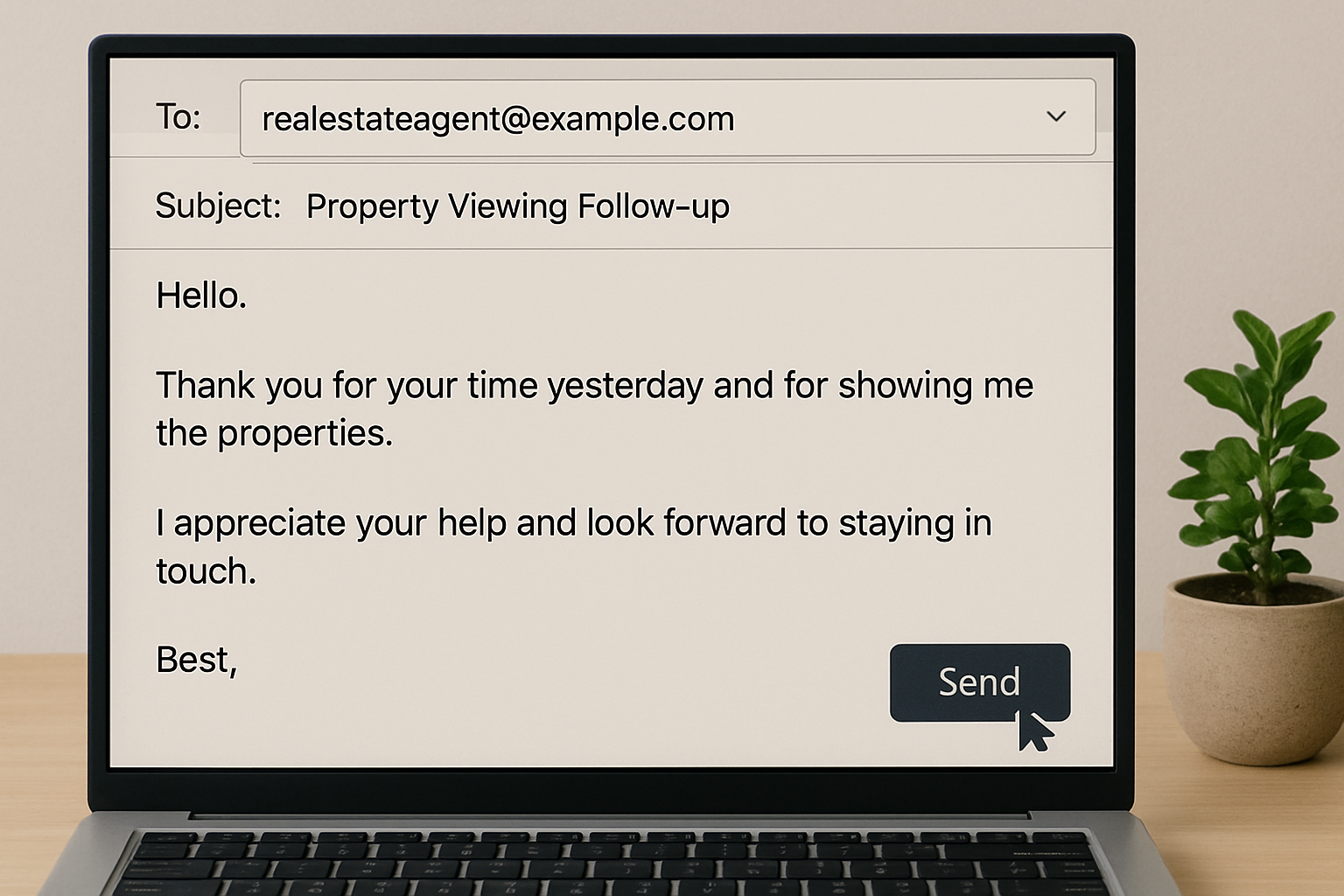不動産投資や賃貸経営を検討される際、「サブリース契約」という言葉を耳にされることが多いのではないでしょうか。
サブリース契約は、物件オーナーにとって安定した収入と管理の手間軽減を実現する魅力的な仕組みである一方、近年トラブル事例も増加しており、慎重な検討が必要な契約形態です。
本記事では、INA&Associates株式会社が、サブリース契約の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、さらにはトラブル回避のポイントまで、不動産の専門知識を平易に解説いたします。
これからサブリース契約を検討される方、既に契約中で見直しを考えている方にとって、適切な判断材料となる情報をお届けします。
サブリース契約とは?基本的な仕組みを理解する
サブリース契約の定義
サブリース契約とは、物件オーナー(貸主)が不動産会社(サブリース会社)に物件を一括して貸し出し、そのサブリース会社が入居者(転借人)に転貸する契約形態です。
この仕組みは「一括借り上げ」とも呼ばれ、2つの独立した賃貸借契約によって成り立っています。
第一の契約は、物件オーナーとサブリース会社の間で締結される「マスターリース契約」です。この契約により、サブリース会社は物件オーナーから建物全体を借り受けます。
第二の契約は、サブリース会社と実際の入居者との間で結ばれる「転貸借契約」です。入居者はサブリース会社に家賃を支払い、サブリース会社は物件オーナーに賃料を支払うという構造になります。
管理委託契約との根本的な違い
サブリース契約を理解するためには、従来の管理委託契約との違いを明確に把握することが重要です。
管理委託契約では、物件オーナーが入居者と直接賃貸借契約を結び、管理業務のみを不動産会社に委託します。この場合、賃貸借契約の当事者は物件オーナーと入居者であり、不動産会社は管理業務の代行者という位置づけです。
一方、サブリース契約では、物件オーナーと入居者は直接的な契約関係を持ちません。サブリース会社が中間に位置し、物件オーナーに対しては借主として、入居者に対しては貸主として機能します。
この構造により、物件オーナーは入居者の有無に関わらず、サブリース会社から安定した賃料を受け取ることができる仕組みとなっています。
サブリース契約の法的位置づけ
法的な観点から見ると、サブリース契約におけるサブリース会社は、物件オーナーに対して借地借家法上の「借主」の地位を有します。
これは非常に重要なポイントで、借地借家法第32条により、サブリース会社には賃料増減額請求権が認められています。
この法的位置づけにより、サブリース会社は経済情勢の変化や物件の経年劣化などを理由として、物件オーナーに対して賃料の減額を請求することが可能です。また、契約の解除についても、一般的な賃貸借契約と同様に、正当事由が必要となります。
| 契約形態 | 契約当事者 | 賃料支払い | 管理責任 | 空室リスク |
|---|---|---|---|---|
| 管理委託契約 | オーナー⇔入居者 | 入居者→オーナー | 管理会社が代行 | オーナーが負担 |
| サブリース契約 | オーナー⇔サブリース会社⇔入居者 | サブリース会社→オーナー | サブリース会社 | サブリース会社が負担 |
空室保証と滞納保証の仕組み
サブリース契約の最大の特徴の一つが、空室保証と滞納保証です。
従来の賃貸経営では、空室が発生すると家賃収入が途絶え、入居者の家賃滞納があると回収に苦労するリスクがありました。
サブリース契約では、サブリース会社が物件オーナーに対して一定の賃料を保証します。たとえ実際の入居者がいない期間があっても、また入居者が家賃を滞納したとしても、サブリース会社は契約に基づいて物件オーナーに賃料を支払い続けます。
この保証により、物件オーナーは安定した収入を確保できるのです。
ただし、この保証には「免責期間」が設定される場合があります。免責期間とは、新築時の募集開始から入居者決定まで、または退去後の次の入居者決定までの一定期間において、サブリース会社が賃料支払い義務を免除される期間のことです。
契約前には、この免責期間の有無と期間について必ず確認することが重要です。
サブリース契約の5つの主要メリット
1.安定した収入の確保
サブリース契約の最大のメリットは、安定した収入を確保できることです。
通常の賃貸経営では、空室が発生すると家賃収入が途絶えてしまいますが、サブリース契約では空室の有無に関わらず、サブリース会社から一定の賃料を受け取ることができます。
この安定性は、特に不動産投資ローンを利用している物件オーナーにとって大きなメリットとなります。毎月のローン返済額が固定されている中で、家賃収入も安定していることで、キャッシュフローの予測が立てやすくなり、資金計画を確実に実行できます。
また、賃貸市場の変動や経済情勢の影響を直接受けにくいという特徴もあります。景気悪化により空室率が上昇した場合でも、サブリース契約であれば契約期間中は安定した収入を維持できるため、不動産投資のリスクを大幅に軽減できます。
2.賃貸管理業務からの完全解放
サブリース契約では、賃貸管理に関するすべての業務をサブリース会社に一任できます。
具体的には、以下の業務が含まれます:
- 入居者募集と審査
- 賃貸借契約の締結
- 家賃の集金と督促
- 入居者からの問い合わせ対応
- 設備故障時の修理手配
- 退去時の立会いと原状回復工事
- 契約更新手続き
管理委託契約の場合、設備の修繕や入居者トラブルの対応について、最終的な判断は物件オーナーが行う必要があります。
しかし、サブリース契約では、サブリース会社が借主として入居者と直接契約を結んでいるため、これらの判断もすべてサブリース会社が行います。
この完全な業務委託により、物件オーナーは賃貸経営の煩雑な作業から解放され、本業に集中することができます。特に、海外居住者や高齢の物件オーナー、複数物件を所有する投資家にとって、この利便性は非常に価値の高いものです。
3.賃貸経営初心者への安心感
不動産投資や賃貸経営の経験が浅い方にとって、サブリース契約は安心して始められる仕組みです。
賃貸経営には、入居者審査、家賃設定、トラブル対応など、専門知識と経験が必要な業務が多数あります。
サブリース契約では、これらの専門的な業務をすべて経験豊富なサブリース会社が担当するため、初心者でも安心して賃貸経営を開始できます。また、入居者との直接的なやり取りがないため、トラブル対応のストレスからも解放されます。
さらに、サブリース会社は地域の賃貸市場に精通しており、適切な家賃設定や効果的な募集活動を行うことができます。個人の物件オーナーが単独で行うよりも、より効率的で効果的な賃貸経営が期待できます。
4.入居者トラブルの回避
賃貸経営において最も頭を悩ませる問題の一つが、入居者とのトラブルです。
家賃滞納、近隣住民とのトラブル、設備の不適切な使用、退去時の原状回復をめぐる争いなど、様々な問題が発生する可能性があります。
サブリース契約では、入居者との契約当事者はサブリース会社であるため、これらのトラブル対応もすべてサブリース会社が行います。物件オーナーは入居者と直接関わることがないため、精神的な負担を大幅に軽減できます。
また、サブリース会社は多数の物件を管理しているため、トラブル対応のノウハウと経験が豊富です。法的な問題が発生した場合でも、適切な対応を期待できます。
5.相続税対策としての効果
サブリース契約は、相続税対策としても有効な手段です。
賃貸用不動産は、自用地と比較して相続税評価額が低くなるため、相続税の軽減効果があります。
サブリース契約により安定した賃貸経営が実現できれば、相続時まで継続的に賃貸用不動産として評価を受けることができます。また、相続人が賃貸経営の経験がない場合でも、サブリース契約であれば安心して相続財産を引き継ぐことができます。
| メリット | 具体的効果 | 特に有効な対象者 |
|---|---|---|
| 安定収入 | 空室・滞納リスクの回避 | ローン利用者、年金生活者 |
| 管理業務委託 | 時間と労力の節約 | 本業多忙者、遠隔地居住者 |
| 初心者安心 | 専門知識不要 | 不動産投資初心者 |
| トラブル回避 | 精神的負担軽減 | ストレス回避重視者 |
| 相続税対策 | 評価額軽減効果 | 高額資産保有者 |
サブリース契約の6つの主要デメリットと注意点
1.高額な手数料による収益性の低下
サブリース契約の最大のデメリットは、手数料の高さです。
サブリース会社への手数料は、一般的に賃料の10~20%程度に設定されており、管理委託契約の手数料(5~10%程度)と比較すると、2倍程度の負担となります。
例えば、月額家賃10万円の物件の場合、管理委託契約では月額5,000~10,000円の手数料で済むところ、サブリース契約では10,000~20,000円の手数料が発生します。年間で考えると、60,000~120,000円の差額が生じることになります。
この手数料の差は、長期間にわたって累積すると非常に大きな金額となります。投資収益率(ROI)を重視する投資家にとって、この収益性の低下は重要な検討要素となります。
2.入居者選定権の放棄
サブリース契約では、入居者の選定権を物件オーナーが持つことができません。
入居者の審査や選定は、すべてサブリース会社が行います。これにより、物件オーナーの意向に沿わない入居者が住む可能性があります。
例えば、ファミリー向けの物件として設計した場合でも、サブリース会社の判断でシェアハウスとして運用される可能性があります。また、物件オーナーが望まない属性の入居者(ペット飼育者、喫煙者など)が入居する場合もあります。
この問題は、物件の長期的な価値維持や近隣との関係性に影響を与える可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
3.家賃保証額の定期的な見直しリスク
サブリース契約における家賃保証は、永続的なものではありません。
多くの契約では、2~3年ごとに家賃保証額の見直しが行われ、市場相場の変動や物件の経年劣化を理由として、保証額が減額される可能性があります。
借地借家法第32条により、サブリース会社には賃料減額請求権が認められているため、物件オーナーがこの減額要求を拒否することは困難です。実際に、多くのサブリース契約において、契約更新時に保証額が段階的に減額されているのが現状です。
この見直しにより、当初想定していた収益計画が大幅に狂う可能性があるため、契約時には将来的な減額リスクを十分に考慮した資金計画を立てることが重要です。
4.免責期間による収入空白
多くのサブリース契約には、免責期間が設定されています。
免責期間とは、以下のような期間において、サブリース会社が賃料支払い義務を免除される期間のことです:
- 新築物件の竣工から入居者決定まで
- 入居者退去から次の入居者決定まで
- 大規模修繕工事期間中
免責期間は通常1~3ヶ月程度ですが、立地条件や物件の条件によってはより長期間となる場合があります。この期間中は家賃収入が完全に途絶えるため、ローン返済や固定費の支払いに支障をきたす可能性があります。
5.修繕費用とリフォーム費用の負担継続
サブリース契約を締結しても、物件の修繕費用やリフォーム費用は物件オーナーの負担となります。
経年劣化による設備の交換、外壁や屋根の修繕、室内のリフォームなど、物件維持に必要な費用はすべて物件オーナーが支払う必要があります。
特に築年数が経過した物件では、これらの費用が年々増加する傾向にあります。サブリース会社によっては、修繕工事を指定業者で行うことを条件としている場合があり、工事費用が割高になる可能性もあります。
また、サブリース会社が入居者募集のために必要と判断したリフォーム工事について、物件オーナーに費用負担を求める場合もあります。これらの費用は事前に予測が困難であるため、十分な資金準備が必要です。
6.契約解除の困難性
サブリース契約は、簡単に解除することができません。
サブリース会社は借地借家法上の借主であるため、物件オーナーからの一方的な契約解除には正当事由が必要となります。
正当事由として認められるのは、以下のような場合に限定されます:
- 物件オーナーが自己使用する必要がある場合
- 建物の老朽化により建て替えが必要な場合
- サブリース会社が契約違反を行った場合
これらの正当事由に加えて、多くの場合、立ち退き料の支払いも必要となります。立ち退き料の相場は、残存契約期間の賃料相当額や、サブリース会社の移転費用などを考慮して決定されるため、高額になる可能性があります。
| デメリット | 影響度 | 対策の可能性 | 注意すべき契約者 |
|---|---|---|---|
| 高額手数料 | 高 | 契約前の比較検討 | 収益重視投資家 |
| 入居者選定権なし | 中 | 契約条件での制限 | 物件価値重視者 |
| 家賃見直し | 高 | 見直し条件の確認 | 長期保有予定者 |
| 免責期間 | 中 | 期間短縮交渉 | ローン利用者 |
| 修繕費負担 | 高 | 修繕計画の策定 | 築古物件所有者 |
| 解約困難 | 高 | 解約条件の確認 | 短期保有予定者 |
サブリース契約でよく発生するトラブル事例と対処法
1.賃料減額トラブル
最も頻繁に発生するトラブルが、サブリース会社からの賃料減額要求です。
契約当初は「30年間家賃保証」などの魅力的な条件で契約したにも関わらず、数年後に大幅な賃料減額を要求されるケースが多発しています。
具体的事例
ある物件オーナーは、新築アパートをサブリース契約で月額80万円の家賃保証で契約しました。しかし、3年後の契約更新時に「周辺相場の下落」を理由として月額65万円への減額を要求され、年間180万円の収入減少となりました。
法的背景と対処法
借地借家法第32条により、サブリース会社の賃料減額請求権は法的に認められています。過去の判例では、物件オーナーがこの減額要求を拒否して訴訟を起こしても、ほとんどの場合でサブリース会社側が勝訴しています。
対処法:
- 契約前に賃料見直し条件を詳細に確認する
- 減額幅の上限を契約書に明記する
- 複数のサブリース会社の条件を比較検討する
- 将来的な減額を見込んだ資金計画を立てる
2.契約解除困難トラブル
物件オーナーがサブリース契約の解除を希望しても、サブリース会社が応じないトラブルが増加しています。
具体的事例
相続により物件を取得した方が、自己居住のためにサブリース契約の解除を申し入れたところ、サブリース会社から「正当事由がない」として拒否され、さらに違約金として残存契約期間の賃料相当額(約500万円)を要求されました。
法的背景と対処法
サブリース会社は借地借家法上の借主であるため、物件オーナーからの契約解除には正当事由と立ち退き料が必要です。
対処法:
- 契約時に解除条件を明確に定める
- 正当事由の要件を事前に確認する
- 弁護士などの専門家に相談する
- 双方合意による解除を粘り強く交渉する
3.サブリース会社破綻トラブル
サブリース会社の経営破綻により、家賃の支払いが停止されるトラブルも発生しています。
具体的事例
2018年に発覚した「かぼちゃの馬車問題」では、サブリース会社の破綻により、多数の物件オーナーが家賃収入を失い、ローン返済に窮する事態となりました。
対処法
予防策:
- サブリース会社の財務状況を事前に調査する
- 上場企業や大手企業系列の会社を選択する
- 複数の物件を異なるサブリース会社に分散する
破綻時の対応:
- 賃料不払いを理由とした契約解除を検討する
- 入居者との直接契約への移行を図る
- 弁護士に相談して法的手続きを進める
4.説明不足によるトラブル
契約前の重要事項説明が不十分で、物件オーナーが契約内容を十分理解していなかったことによるトラブルも多発しています。
具体的事例
「家賃保証」という言葉から永続的な保証と理解していた物件オーナーが、実際には定期的な見直しがあることを契約後に知り、「説明が不十分だった」として訴訟に発展したケースがあります。
対処法
- 契約前に重要事項説明書を詳細に確認する
- 不明な点は必ず質問して明確にする
- 口約束ではなく、すべて書面で確認する
- 第三者(弁護士等)による契約書チェックを依頼する
5.修繕費用トラブル
修繕工事の実施や費用負担をめぐるトラブルも頻発しています。
具体的事例
サブリース会社が「入居者確保のために必要」として室内リフォームを実施し、後日物件オーナーに200万円の費用請求を行ったケースがあります。物件オーナーは事前承諾していないとして支払いを拒否し、トラブルとなりました。
対処法
- 修繕工事の承諾手続きを契約書で明確化する
- 工事費用の上限額を設定する
- 複数業者からの見積もり取得を義務化する
- 定期的な物件状況報告を求める
| トラブル種類 | 発生頻度 | 解決困難度 | 主な対策 |
|---|---|---|---|
| 賃料減額 | 非常に高 | 高 | 契約条件の詳細確認 |
| 契約解除困難 | 高 | 非常に高 | 解除条件の事前明確化 |
| 会社破綻 | 低 | 非常に高 | 会社選定の慎重化 |
| 説明不足 | 中 | 中 | 第三者チェック |
| 修繕費用 | 中 | 中 | 承諾手続きの明確化 |
まとめ:サブリース契約成功のための重要ポイント
サブリース契約は、適切に活用すれば物件オーナーにとって非常に有効な賃貸経営手法です。しかし、その一方で多くのリスクとデメリットも存在するため、慎重な検討と適切な対策が不可欠です。
サブリース契約が適している方
以下の条件に該当する方には、サブリース契約が適している可能性があります:
1.賃貸経営初心者の方
専門知識や経験がなくても、プロフェッショナルなサブリース会社に管理を任せることで、安心して賃貸経営を開始できます。
2.本業が多忙な方
賃貸管理業務に時間を割くことが困難な方にとって、完全な業務委託は大きなメリットとなります。
3.遠隔地に物件を所有する方
物件から離れた場所に居住している場合、現地での管理業務は困難です。サブリース契約により、距離の問題を解決できます。
4.安定収入を重視する方
多少の収益性低下を受け入れても、安定した収入を確保したい方には適しています。
契約前に必ず確認すべき重要事項
サブリース契約を検討される際は、以下の点を必ず確認してください:
1.賃料見直し条件
- 見直し頻度(通常2~3年ごと)
- 見直し基準(市場相場、経年劣化等)
- 減額幅の上限設定の有無
2.免責期間の詳細
- 免責期間の長さ
- 免責期間が適用される具体的条件
- 免責期間中の費用負担
3.解約条件
- 解約に必要な正当事由
- 解約予告期間
- 違約金や立ち退き料の算定方法
4.修繕費用の取り扱い
- 修繕工事の承諾手続き
- 費用負担の範囲と上限
- 工事業者の選定権
5.サブリース会社の信頼性
- 財務状況の健全性
- 過去のトラブル履歴
- 管理実績と評判
次のアクションステップ
サブリース契約を検討されている方は、以下のステップで進めることをお勧めします:
1.複数社からの提案取得
最低3社以上のサブリース会社から提案を取得し、条件を比較検討してください。
2.専門家への相談
不動産に精通した弁護士や税理士に契約内容をチェックしてもらうことで、リスクを最小化できます。
3.資金計画の見直し
将来的な賃料減額を見込んだ保守的な資金計画を策定してください。
4.定期的な契約見直し
契約後も定期的に条件を見直し、必要に応じて交渉や契約変更を検討してください。
サブリース契約は、正しく理解し適切に活用すれば、安定した賃貸経営を実現する有効な手段です。しかし、安易な判断は大きな損失につながる可能性があります。
十分な検討と準備を行い、納得のいく契約を締結されることを強くお勧めいたします。
INA&Associates株式会社では、サブリース契約に関するご相談も承っております。お客様の状況に応じた最適な賃貸経営手法をご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
Q1.サブリース契約の家賃保証は本当に永続的ですか?
A1.いいえ、永続的ではありません。多くのサブリース契約では、2~3年ごとに家賃保証額の見直しが行われます。
借地借家法第32条により、サブリース会社には賃料減額請求権が認められているため、市場相場の変動や物件の経年劣化を理由として、保証額が減額される可能性があります。
契約時には「家賃保証」という言葉に惑わされず、見直し条件を詳細に確認することが重要です。
Q2.サブリース契約は途中で解約できますか?
A2.解約は可能ですが、非常に困難です。
サブリース会社は借地借家法上の借主であるため、物件オーナーからの一方的な契約解除には正当事由が必要となります。正当事由として認められるのは、自己使用の必要性、建物の老朽化による建て替え、契約違反などに限定されます。
また、多くの場合、立ち退き料の支払いも必要となるため、解約には高額な費用が発生する可能性があります。
Q3.サブリース契約の手数料相場はどの程度ですか?
A3.サブリース契約の手数料は、一般的に賃料の10~20%程度です。
これは管理委託契約の手数料(5~10%程度)と比較すると、約2倍の水準となります。例えば、月額家賃10万円の物件の場合、年間12~24万円の手数料が発生します。
この手数料の差は長期間にわたって累積すると大きな金額となるため、収益性を重視する場合は慎重に検討する必要があります。
Q4.修繕費用やリフォーム費用は誰が負担しますか?
A4.修繕費用やリフォーム費用は、原則として物件オーナーの負担となります。
経年劣化による設備の交換、外壁や屋根の修繕、室内のリフォームなど、物件維持に必要な費用はすべて物件オーナーが支払います。ただし、入居者の故意・過失による損傷については、入居者負担となる場合があります。
契約前には、修繕工事の承諾手続きや費用負担の範囲について明確に定めておくことが重要です。
Q5.サブリース会社が破綻した場合はどうなりますか?
A5.サブリース会社が破綻した場合、家賃の支払いが停止される可能性があります。
この場合、物件オーナーは賃料不払いを理由としてサブリース契約を解除し、入居者と直接契約を結ぶことが可能です。ただし、入居者との契約移行には時間がかかる場合があり、その間の収入確保が困難になる可能性があります。
このリスクを回避するため、契約前にはサブリース会社の財務状況を十分に調査し、信頼性の高い会社を選択することが重要です。

稲澤大輔
INA&Associates株式会社 代表取締役。大阪・東京・神奈川を拠点に、不動産売買・賃貸仲介・管理を手掛ける。不動産業界での豊富な経験をもとに、サービスを提供。 「企業の最も重要な資産は人財である」という理念のもと、人財育成を重視。持続可能な企業価値の創造に挑戦し続ける。 【取得資格(合格資格含む)】 宅地建物取引士、行政書士、個人情報保護士、マンション管理士、管理業務主任者、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、賃貸不動産経営管理士、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者、不動産コンサルティングマスター

.png)