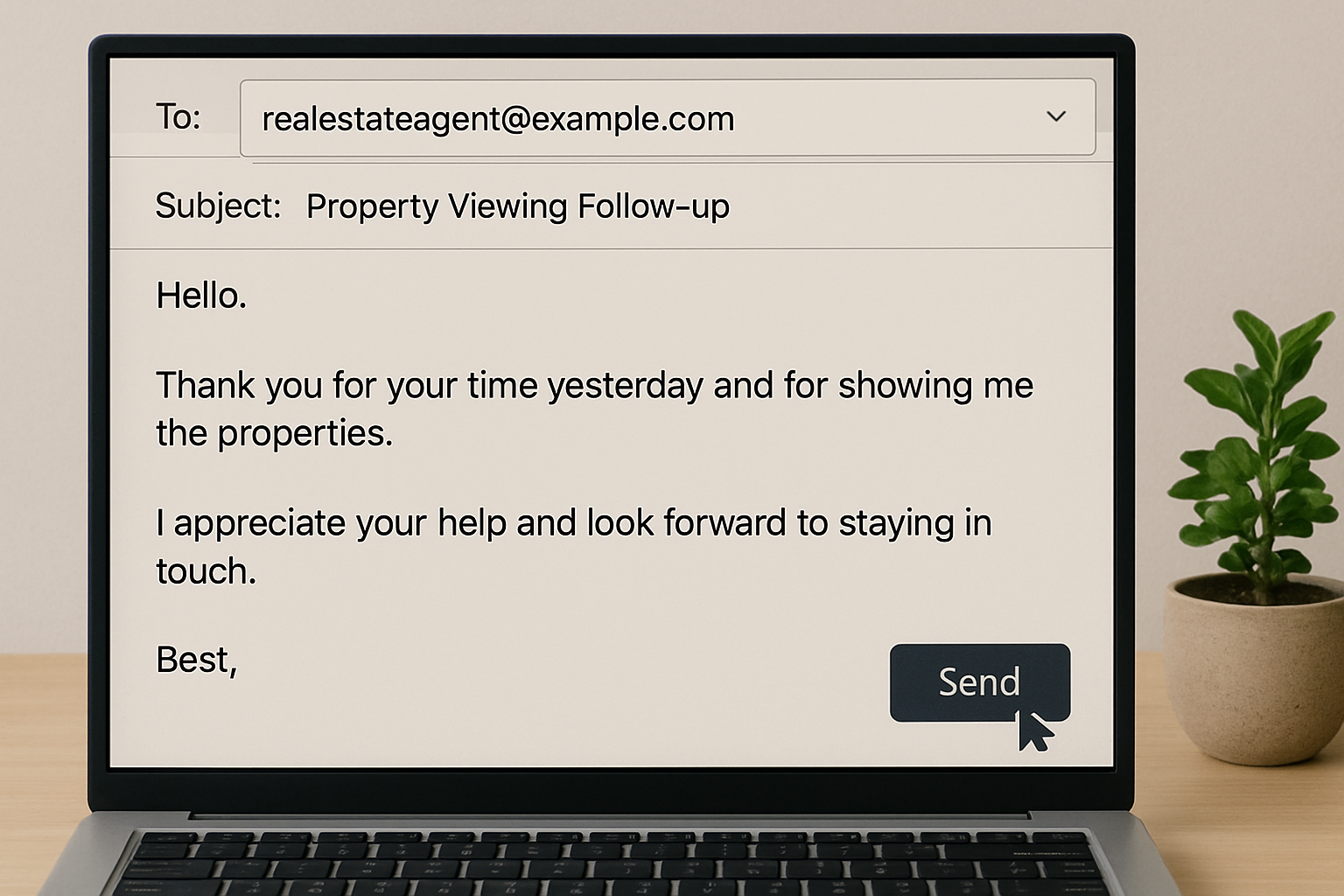不動産投資への関心が高まる中、「どのように始めればよいのか分からない」「失敗するリスクが心配」といった声を多くの方からお聞きします。INA&Associates株式会社として、長年にわたり不動産業界に携わり、多くの投資家の皆様をサポートしてまいりました。
2025年の不動産投資市場は、金利動向や税制改正の影響を受けながらも、依然として魅力的な投資手段として注目されています。本記事では、不動産投資の基礎知識から物件購入、そして管理・運用まで、初心者の方でも理解できるよう体系的に解説いたします。
不動産投資は正しい知識と適切な手順を踏むことで、安定した収益を得られる投資手法です。本記事を通じて、皆様が自信を持って不動産投資を始められるよう、実践的な情報をお届けいたします。
不動産投資とは?基礎知識と2025年の市場動向
不動産投資の定義と仕組み
不動産投資とは、マンションやアパート、戸建て住宅などの不動産を購入し、賃貸収入(インカムゲイン)や売却益(キャピタルゲイン)を得る投資手法です。株式投資や債券投資と比較して、物理的な資産を保有するため、インフレヘッジ効果や相続税対策としても活用されています。
不動産投資の収益構造は主に以下の2つに分類されます。
インカムゲイン(賃貸収入)は、物件を第三者に貸し出すことで得られる継続的な収入です。毎月安定した家賃収入が期待でき、長期的な資産形成に適しています。一方、キャピタルゲイン(売却益)は、購入時より高い価格で物件を売却することで得られる利益です。市場動向や立地条件により大きく左右されるため、タイミングの見極めが重要となります。
2025年の市場動向と投資環境
2025年の不動産投資市場は、複数の要因が複雑に絡み合う環境となっています。日本銀行の金融政策正常化により、不動産投資ローンの金利は上昇傾向にありますが、投資額は2024年通年で5兆円に達し、コロナ前の2019年を超える水準となっています。
建築コストの高騰が続く一方で、都心部を中心とした不動産価格の上昇により、利回りは横ばいから微減の傾向を示しています。しかし、賃料相場の上昇が価格上昇を一部相殺しており、適切な物件選択により収益性を確保することは十分可能です。
他の投資手法との比較
不動産投資の特徴を理解するため、主要な投資手法との比較を以下の表にまとめました。
| 投資手法 | 初期投資額 | 流動性 | 収益性 | リスク | 管理の手間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不動産投資 | 高(数百万円〜) | 低 | 中〜高 | 中 | 高 |
| 株式投資 | 低(数万円〜) | 高 | 高 | 高 | 低 |
| 債券投資 | 中(数十万円〜) | 中 | 低〜中 | 低 | 低 |
| J-REIT | 低(数万円〜) | 高 | 中 | 中 | 低 |
不動産投資は初期投資額が高く、流動性が低いというデメリットがありますが、安定した収益性と物理的資産の保有による安心感が大きなメリットとなります。また、レバレッジ効果により、自己資金以上の投資が可能な点も特徴的です。
不動産投資のメリット・デメリット
主要なメリット9選
1.安定した収入源の確保
不動産投資の最大のメリットは、毎月安定した家賃収入を得られることです。株式の配当金と異なり、入居者がいる限り継続的な収入が期待できます。適切な立地の物件であれば、長期間にわたって安定した収益を確保することが可能です。
2.インフレヘッジ効果
物価上昇局面では、不動産価格や家賃も連動して上昇する傾向があります。現金や預金では目減りしてしまう資産価値を、不動産投資により保全することができます。
3.レバレッジ効果の活用
不動産投資ローンを活用することで、自己資金の数倍の投資が可能となります。例えば、自己資金500万円で2,000万円の物件を購入し、より大きな収益を狙うことができます。
4.生命保険代わりの効果
投資用ローンには団体信用生命保険が付帯されており、万が一の際にはローン残債が完済されます。残された家族には無借金の収益物件が相続され、継続的な収入源となります。
5.相続税対策
不動産は相続税評価額が時価より低く算定されるため、現金で保有するより相続税を軽減できます。特に賃貸物件の場合、さらに評価額が下がる仕組みとなっています。
6.所得税・住民税の節税効果
不動産投資で発生する減価償却費や各種経費により、給与所得と損益通算することで所得税・住民税の軽減が可能です。特に課税所得が900万円以上の方には大きな節税効果が期待できます。
7.年金代わりの収入
公的年金制度への不安が高まる中、不動産投資による家賃収入は私的年金として機能します。定年退職後も継続的な収入源を確保できます。
8.資産価値の保全
土地は有限な資源であり、特に人口集中地域では長期的な価値保全が期待できます。建物部分は減価しますが、適切なメンテナンスにより資産価値を維持することが可能です。
9.事業としての拡張性
成功体験を積み重ねることで、複数物件の保有や規模拡大が可能となります。不動産投資を事業として発展させ、より大きな収益を目指すことができます。
注意すべきデメリット8選
1.空室リスク
最も重要なリスクは空室の発生です。入居者がいなければ家賃収入は得られず、ローン返済や管理費の負担が続きます。立地選択や適切な家賃設定により、このリスクを最小限に抑える必要があります。
2.家賃滞納リスク
入居者による家賃滞納が発生する可能性があります。滞納が長期化すると、法的手続きによる解決が必要となり、時間と費用がかかります。
3.修繕・メンテナンス費用
建物の老朽化に伴い、定期的な修繕やメンテナンスが必要となります。エアコンや給湯器の交換、外壁塗装など、まとまった費用が発生することがあります。
4.金利上昇リスク
変動金利でローンを組んでいる場合、金利上昇により返済額が増加するリスクがあります。2025年の金融環境では特に注意が必要です。
5.不動産価値下落リスク
経済情勢や地域の人口減少により、物件価値が下落する可能性があります。売却時に購入価格を下回るリスクを考慮する必要があります。
6.流動性の低さ
不動産は株式と比較して売却に時間がかかります。急な資金需要に対応しにくく、現金化までに数ヶ月を要することがあります。
7.災害リスク
地震や火災、水害などの自然災害により、物件が損傷するリスクがあります。保険加入により一定の補償は受けられますが、完全な復旧は困難な場合があります。
8.管理の手間
入居者対応や物件管理には相応の時間と労力が必要です。管理会社に委託することで軽減できますが、委託費用が発生します。
リスク対策の基本方針
| リスク項目 | 主な対策 | 効果 |
|---|---|---|
| 空室リスク | 立地重視・適正家賃設定 | 高 |
| 家賃滞納 | 入居審査強化・保証会社利用 | 中 |
| 修繕費用 | 修繕積立・新築/築浅物件選択 | 中 |
| 金利上昇 | 固定金利選択・繰上返済 | 中 |
| 価値下落 | 立地・将来性重視 | 高 |
| 災害リスク | 保険加入・耐震性確認 | 中 |
適切なリスク管理により、不動産投資のデメリットを最小限に抑えながら、安定した収益を確保することが可能です。
不動産投資の始め方|購入までの10ステップ
ステップ1:投資目的と予算の明確化
不動産投資を始める前に、明確な目的と予算を設定することが重要です。投資目的は「老後の年金代わり」「相続税対策」「副収入の確保」など、人それぞれ異なります。目的により適切な投資戦略や物件タイプが変わるため、最初に明確化しておく必要があります。
予算設定では、自己資金と借入可能額を正確に把握します。一般的に、物件価格の20〜30%の自己資金が必要とされており、年収の7〜10倍程度の借入が可能とされています。ただし、属性(年収、勤務先、年齢など)により大きく変動するため、事前に金融機関で相談することをお勧めします。
ステップ2:不動産投資の勉強と情報収集
成功する不動産投資には、十分な知識習得が不可欠です。書籍やセミナー、インターネットを活用して基礎知識を身につけましょう。特に以下の分野について理解を深めることが重要です。
不動産市場の動向、税制や法律、融資制度、物件評価方法、賃貸管理の実務など、幅広い知識が必要となります。また、実際の投資家の体験談や失敗事例を学ぶことで、リスクを事前に把握することができます。
ステップ3:投資スタイルの決定
不動産投資には複数のスタイルがあり、自身の資金力や時間、リスク許容度に応じて選択する必要があります。主な投資スタイルは以下の通りです。
ワンルームマンション投資は、比較的少額から始められ、管理の手間が少ないため初心者に適しています。一方、一棟アパート・マンション投資は、より大きな収益が期待できますが、初期投資額と管理の負担が大きくなります。
戸建て投資は、土地付きのため資産価値が安定しており、ファミリー層をターゲットとするため長期入居が期待できます。商業用不動産投資は、高い利回りが期待できる反面、テナントリスクや市場変動の影響を受けやすい特徴があります。
ステップ4:物件選びのポイント
物件選びは不動産投資成功の最重要要素です。以下の観点から総合的に評価する必要があります。
立地条件では、最寄り駅からの距離、周辺環境、将来の開発計画などを確認します。駅徒歩10分以内、商業施設や医療機関の充実、治安の良さなどが重要な要素となります。
物件の状態については、築年数、構造、設備の状況を詳しく調査します。新築物件は設備が新しく入居者に人気がありますが、価格が高く利回りが低い傾向があります。中古物件は価格が安く高利回りが期待できますが、修繕費用の発生リスクがあります。
収益性の評価では、表面利回りだけでなく実質利回りを計算し、周辺相場と比較検討します。表面利回りが相場より著しく高い物件は、何らかの問題を抱えている可能性があるため注意が必要です。
ステップ5:現地調査と物件評価
気になる物件が見つかったら、必ず現地調査を実施します。インターネットや資料だけでは分からない情報を直接確認することが重要です。
現地調査では、物件の外観や共用部分の状態、周辺環境、交通アクセス、商業施設の充実度などを確認します。また、異なる時間帯に訪問することで、騒音や治安の状況も把握できます。
物件評価では、類似物件との比較分析を行い、適正価格を判断します。不動産会社から提供される資料だけでなく、自身でも周辺の賃貸相場や売買事例を調査し、客観的な評価を行うことが重要です。
ステップ6:資金調達とローン申請
物件が決まったら、資金調達の準備を進めます。不動産投資ローンの金利相場は、2025年現在で年1.5〜4.0%程度となっており、金融機関や借入条件により大きく異なります。
複数の金融機関で事前審査を受け、最も有利な条件を提示する機関を選択します。都市銀行、地方銀行、信用金庫、ノンバンクなど、それぞれ特徴が異なるため、比較検討が重要です。
審査に必要な書類は、源泉徴収票、確定申告書、物件資料、自己資金証明書などです。審査期間は通常1〜2週間程度ですが、物件や借入条件により変動します。
ステップ7:買付申込と条件交渉
融資の目処が立ったら、売主に対して買付申込を行います。買付申込書には、購入希望価格、融資条件、引き渡し希望日などを記載します。
価格交渉では、物件の状況や市場相場を踏まえて適切な価格を提示します。売主の売却理由や急ぎ度により、交渉の余地が変わるため、不動産会社から情報を収集することが重要です。
その他の条件として、設備の修繕や清掃、現入居者の契約条件の引き継ぎなども交渉対象となります。
ステップ8:売買契約の締結
買付申込が受諾されたら、売買契約を締結します。契約前には重要事項説明を受け、物件の詳細情報や契約条件を十分に確認します。
契約時には手付金(通常は売買価格の5〜10%)を支払います。契約後の解約は手付金の放棄や違約金の支払いが必要となるため、慎重に判断する必要があります。
契約書には、売買価格、引き渡し日、融資特約、瑕疵担保責任などの重要事項が記載されているため、不明な点は必ず確認しましょう。
ステップ9:融資実行と決済
売買契約締結後、金融機関で正式な融資申込を行います。本審査では、契約書や重要事項説明書などの追加書類が必要となります。
融資承認後、決済日を調整します。決済では、残代金の支払い、所有権移転登記、鍵の引き渡しなどが同時に行われます。司法書士が立ち会い、法的手続きを確実に実行します。
ステップ10:物件引き渡し
決済完了後、物件の引き渡しを受けます。現入居者がいる場合は、賃貸借契約や敷金・礼金の引き継ぎを行います。
引き渡し後は、火災保険の加入、管理会社との契約、確定申告の準備など、運用開始に向けた手続きを進めます。
以上の10ステップを着実に実行することで、安全かつ確実に不動産投資を始めることができます。各ステップで専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。
物件購入後の管理・運用のやり方
賃貸管理の基本業務
物件購入後の成功は、適切な賃貸管理にかかっています。賃貸管理業務は大きく「入居者管理」と「建物管理」に分類されます。
入居者管理では、入居者募集、入居審査、契約手続き、家賃回収、退去手続きなどを行います。入居者との良好な関係を維持することで、長期入居を促進し、安定した収益を確保できます。
建物管理では、日常清掃、設備点検、修繕対応、法定点検などを実施します。適切なメンテナンスにより物件価値を維持し、入居者満足度を高めることができます。
これらの業務は自主管理と管理委託の2つの方法があります。自主管理は費用を抑えられますが、時間と労力が必要です。管理委託は費用がかかりますが、専門的なサービスを受けられ、オーナーの負担を軽減できます。
管理会社の選び方
管理委託を選択する場合、適切な管理会社の選定が重要です。以下の観点から総合的に評価しましょう。
客付け力は最も重要な要素です。管理物件の入居率が95%以上を維持している会社を選びましょう。空室期間の短縮は収益に直結するため、実績のある会社を選ぶことが重要です。
管理戸数も重要な指標です。1万戸以上の管理実績がある会社は、ノウハウの蓄積と組織体制が整っていると考えられます。ただし、大手だけでなく地域密着型の会社も検討対象となります。
担当者の対応を確認しましょう。レスポンスの速さ、提案力、専門知識の豊富さなどを面談で評価します。長期的な付き合いとなるため、信頼できる担当者がいる会社を選ぶことが重要です。
管理委託費の相場は家賃収入の5%前後です。安すぎる会社はサービス品質に問題がある可能性があり、高すぎる会社は収益性を圧迫します。適正な価格でサービス内容を比較検討しましょう。
空室対策と家賃設定
空室リスクを最小限に抑えるため、効果的な空室対策を実施する必要があります。
適正な家賃設定が最も重要です。周辺相場より高すぎると入居者が決まらず、安すぎると収益性が悪化します。定期的に相場調査を行い、市場に適した家賃を設定しましょう。
物件の魅力向上も効果的です。室内のリフォーム、設備の更新、インターネット環境の整備などにより、競合物件との差別化を図ります。費用対効果を考慮して実施することが重要です。
募集活動の強化では、複数の不動産会社への依頼、インターネット掲載の充実、内見対応の改善などを行います。写真や動画を活用した魅力的な物件紹介も効果的です。
入居条件の見直しも検討しましょう。ペット可、楽器可、外国人可など、条件を緩和することで入居者層を拡大できます。ただし、リスクとのバランスを考慮する必要があります。
修繕・メンテナンス計画
建物の資産価値を維持するため、計画的な修繕・メンテナンスが必要です。
日常メンテナンスでは、共用部分の清掃、設備の点検、小修繕などを定期的に実施します。問題の早期発見により、大規模修繕を予防できます。
大規模修繕は、外壁塗装、屋上防水、給排水設備の更新などです。マンションの場合は修繕積立金で対応しますが、一棟物件の場合は自己負担となります。築年数に応じた修繕計画を立て、資金を準備しておくことが重要です。
設備更新では、エアコン、給湯器、インターホンなどの交換時期を把握し、計画的に実施します。故障してから対応するより、予防的な交換の方が入居者への影響を最小限に抑えられます。
修繕費用の目安は、年間家賃収入の5〜10%程度です。築年数が古い物件ほど修繕費用が増加する傾向があるため、購入時から考慮しておく必要があります。
収支管理と確定申告
不動産投資の収支を正確に把握し、適切な税務処理を行うことが重要です。
収支管理では、家賃収入、管理費、修繕費、ローン返済額、税金などを月次で記録します。専用の会計ソフトやアプリを活用することで、効率的な管理が可能です。
確定申告では、不動産所得の計算を行います。家賃収入から必要経費を差し引いた金額が不動産所得となり、給与所得と合算して税額を計算します。
必要経費には、管理費、修繕費、減価償却費、ローン利息、税金、保険料などが含まれます。適切な経費計上により、税負担を軽減できます。
減価償却は、建物部分の取得価額を法定耐用年数で割って計算します。木造22年、鉄骨造34年、RC造47年が法定耐用年数です。中古物件の場合は、残存耐用年数で計算します。
税務処理が複雑な場合は、税理士に相談することをお勧めします。適切な税務処理により、合法的な節税効果を得ることができます。
成功する不動産投資のポイント
利回り計算の方法
不動産投資の収益性を正確に評価するため、適切な利回り計算が必要です。利回りには複数の種類があり、それぞれ異なる意味を持ちます。
表面利回りは最も基本的な指標で、年間家賃収入を物件価格で割って計算します。計算が簡単で物件比較に便利ですが、経費を考慮していないため実際の収益性とは異なります。
実質利回りは、年間家賃収入から年間経費を差し引いた金額を、物件価格に購入諸費用を加えた金額で割って計算します。より実態に近い収益性を把握できるため、投資判断に重要な指標です。
想定利回りは、満室時の家賃収入を基に計算した利回りです。空室がある物件の潜在的な収益性を評価する際に使用しますが、実際の入居率を考慮する必要があります。
| 利回りの種類 | 計算式 | 特徴 | 活用場面 |
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 年間家賃収入÷物件価格×100 | 簡単・比較しやすい | 物件の初期スクリーニング |
| 実質利回り | (年間家賃収入-年間経費)÷(物件価格+購入諸費用)×100 | 実態に近い | 投資判断・収支計画 |
| 想定利回り | 満室時年間家賃収入÷物件価格×100 | 潜在的収益性 | 空室物件の評価 |
キャッシュフロー利回りも重要な指標です。年間キャッシュフロー(家賃収入-全ての支出)を自己投資額で割って計算し、実際の手残り収益を評価できます。
立地選定の重要性
不動産投資において立地は最も重要な要素です。「立地・立地・立地」と言われるほど、成功の鍵を握っています。
交通アクセスでは、最寄り駅からの距離と路線の利便性を重視します。駅徒歩10分以内が理想的で、複数路線が利用できる駅は特に価値が高くなります。将来的な路線延伸や新駅開業の計画も確認しましょう。
周辺環境の充実度も重要です。スーパー、コンビニ、病院、学校などの生活利便施設が徒歩圏内にあることで、入居者の満足度が向上します。治安の良さも入居者選択の重要な要因となります。
将来性を考慮した立地選択が重要です。人口動態、再開発計画、企業誘致などにより、将来的な需要変化を予測します。人口減少地域や産業衰退地域は避け、成長が期待できる地域を選択しましょう。
ターゲット層に適した立地を選ぶことも重要です。単身者向けなら駅近の利便性を重視し、ファミリー向けなら学校や公園の近さを重視します。高齢者向けなら医療機関や買い物施設の充実度が重要となります。
長期的な視点での運用
不動産投資は長期投資が基本です。短期的な利益を追求するより、長期的な安定収益を目指すことが重要です。
市場サイクルを理解し、適切なタイミングで投資判断を行います。不動産市場は約10年周期で変動すると言われており、購入時期と売却時期の見極めが重要です。
物件の成長性を考慮した投資を行います。築年数の経過とともに家賃は下落しますが、立地の良い物件は下落幅が小さく、長期的な収益性を維持できます。
ポートフォリオの観点から複数物件への分散投資を検討します。地域分散、物件タイプ分散により、リスクを軽減しながら安定した収益を確保できます。
出口戦略も重要な要素です。将来的な売却時期と売却価格を想定し、トータルリターンを最大化する戦略を立てます。相続対策や資産組み替えも考慮した長期計画が必要です。
税制優遇の活用方法
不動産投資では様々な税制優遇を活用できます。適切な活用により、実質的な収益性を向上させることができます。
減価償却による所得税・住民税の軽減効果は大きなメリットです。特に築古物件は短期間で大きな減価償却費を計上でき、高い節税効果が期待できます。
損益通算により、不動産所得の赤字を給与所得と相殺できます。初年度は購入諸費用により赤字となることが多く、大きな節税効果を得られます。
相続税対策では、不動産の相続税評価額が時価の約70〜80%となることを活用します。賃貸物件の場合、さらに借家権割合(30%)と借地権割合を考慮した評価減が適用されます。
小規模宅地等の特例により、居住用や事業用の土地について大幅な評価減が適用されます。適用要件を満たす物件への投資により、相続税を大幅に軽減できます。
ただし、税制は頻繁に改正されるため、最新の情報を確認し、必要に応じて税理士に相談することをお勧めします。
まとめ
不動産投資は適切な知識と戦略により、安定した収益を得られる魅力的な投資手法です。本記事では、初心者の方でも理解できるよう、基礎知識から実践的な運用方法まで体系的に解説いたしました。
重要なポイントを改めて整理いたします。まず、明確な投資目的と適切な予算設定が成功の基盤となります。十分な勉強と情報収集により、リスクを理解した上で投資を開始することが重要です。
物件選びでは立地を最重視し、収益性とリスクのバランスを考慮した判断を行いましょう。購入後の管理・運用では、適切な管理会社の選定と計画的なメンテナンスにより、長期的な資産価値を維持することができます。
次のアクションとして、まずは不動産投資の基礎知識をさらに深め、実際の物件見学や不動産会社との面談を通じて実践的な経験を積むことをお勧めします。金融機関での融資相談により、自身の投資可能額を把握することも重要です。
不動産投資は一朝一夕で成功するものではありません。継続的な学習と市場動向の把握により、変化する環境に適応していくことが必要です。成功する投資家は皆、学び続ける姿勢を持っています。
不動産投資のご相談はINA&Associatesへ
私たちINA&Associates株式会社では、お客様一人ひとりの状況に応じた最適な不動産投資をサポートしております。ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。皆様の資産形成のお手伝いをさせていただきます。
よくある質問(FAQ)
初期資金は物件価格や投資スタイルにより大きく異なります。ワンルームマンション投資の場合、物件価格の20〜30%程度の自己資金が必要で、2,000万円の物件であれば400〜600万円程度となります。これに加えて、仲介手数料、登記費用、火災保険料などの諸費用が物件価格の7〜10%程度必要です。
一棟アパート投資の場合は、より多くの自己資金が必要となり、1億円の物件であれば2,000〜3,000万円程度の自己資金を準備する必要があります。ただし、属性や物件により融資条件は変動するため、事前に金融機関で相談することをお勧めします。
初心者の方には中古マンション投資をお勧めします。理由として、比較的少額から始められること、管理の手間が少ないこと、流動性が高いことが挙げられます。
立地は駅徒歩10分以内、築10〜20年程度の物件が理想的です。新築は価格が高く利回りが低い傾向があり、築古すぎると修繕リスクが高くなります。中古物件は価格と利回りのバランスが良く、初心者でも収益を確保しやすい特徴があります。
ただし、個人の資金力や投資目的により最適な物件タイプは異なるため、専門家に相談して決定することをお勧めします。
管理委託費の相場は家賃収入の5%前後です。例えば、月額家賃10万円の物件であれば、月額5,000円程度の管理費となります。
管理費に含まれる業務内容は会社により異なりますが、一般的には入居者募集、契約手続き、家賃回収、クレーム対応、退去手続きなどが含まれます。建物管理や清掃は別途費用が発生する場合があります。
安すぎる管理費の会社はサービス品質に問題がある可能性があり、高すぎる会社は収益性を圧迫します。費用だけでなく、サービス内容や実績を総合的に評価して選択することが重要です。
空室リスクを抑える最も効果的な方法は立地選択です。駅近で交通利便性が高く、周辺に生活利便施設が充実している物件は空室期間が短くなります。
次に重要なのは適正な家賃設定です。周辺相場より高すぎると入居者が決まらず、定期的な相場調査により市場に適した家賃を設定する必要があります。
物件の魅力向上も効果的です。室内リフォーム、設備更新、インターネット環境の整備などにより、競合物件との差別化を図ります。費用対効果を考慮して実施することが重要です。
管理会社の客付け力も重要な要素です。入居率95%以上を維持している実績のある管理会社を選択しましょう。
不動産投資では様々な節税効果が期待できます。主なものは以下の通りです。
減価償却費による所得税・住民税の軽減が最も大きな効果です。建物部分の取得価額を法定耐用年数で割った金額を毎年経費計上でき、特に課税所得が900万円以上の方には大きな節税効果があります。
損益通算により、不動産所得の赤字を給与所得と相殺できます。初年度は購入諸費用により赤字となることが多く、大きな節税効果を得られます。
相続税対策では、不動産の相続税評価額が時価より低く算定されるため、現金保有より相続税を軽減できます。
ただし、節税のみを目的とした投資は本末転倒です。まずは収益性を重視し、結果として節税効果を得られるという考え方が重要です。

稲澤大輔
INA&Associates株式会社 代表取締役。大阪・東京・神奈川を拠点に、不動産売買・賃貸仲介・管理を手掛ける。不動産業界での豊富な経験をもとに、サービスを提供。 「企業の最も重要な資産は人財である」という理念のもと、人財育成を重視。持続可能な企業価値の創造に挑戦し続ける。 【取得資格(合格資格含む)】 宅地建物取引士、行政書士、個人情報保護士、マンション管理士、管理業務主任者、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、賃貸不動産経営管理士、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者、不動産コンサルティングマスター

.png)