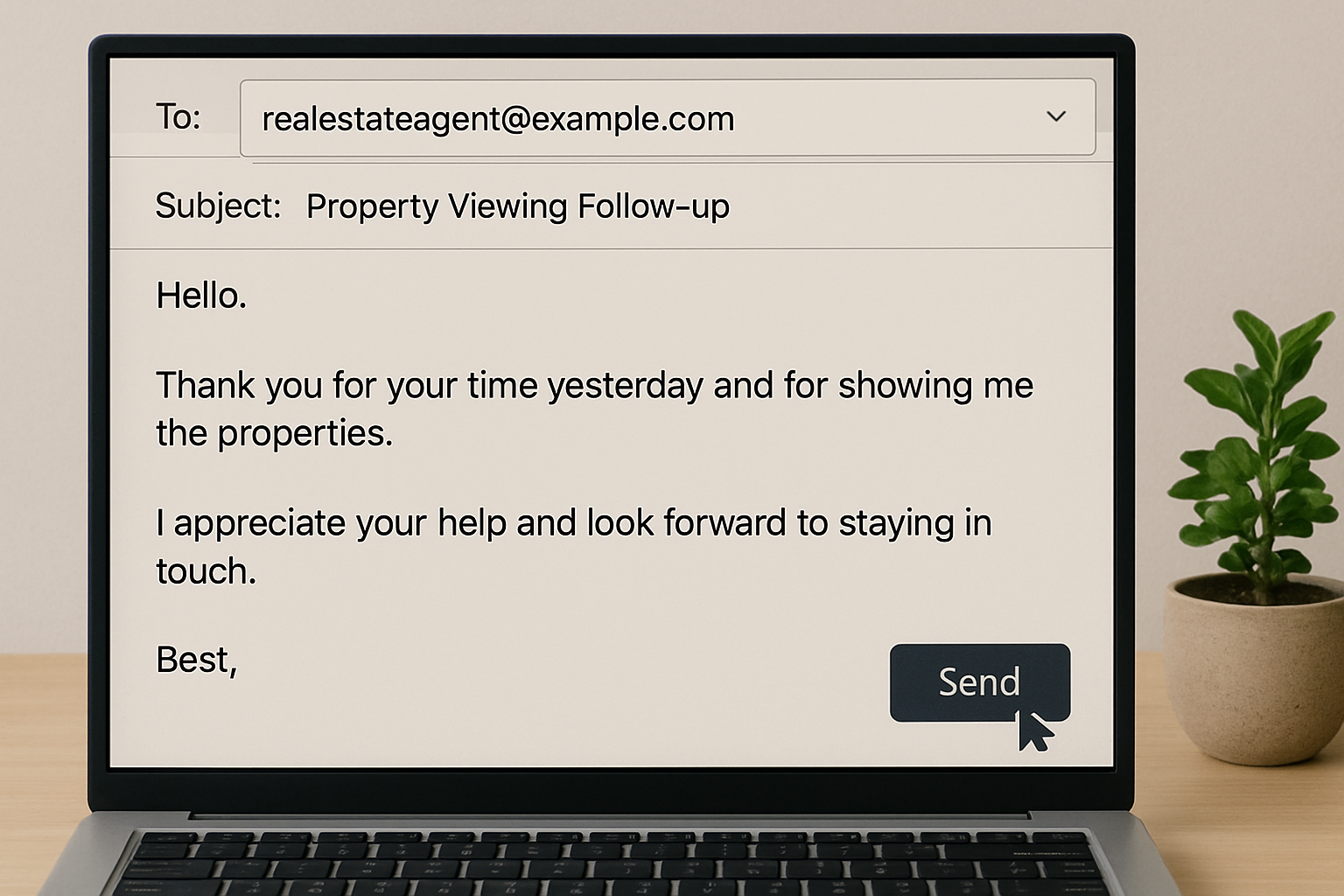築地地区まちづくり事業は、2018年に豊洲市場への移転に伴い閉場した築地市場跡地の大規模再開発プロジェクトです。築地市場の跡地は約19万平方メートル(約19ヘクタール)にも及び、都心では極めて貴重な広大な土地であり、この再開発に大きな期待が寄せられています。東京都はこの土地のポテンシャルを最大限に活かし、都心と臨海部を結びつける新たな都市拠点づくりを目指しています。歴史ある築地の「食文化」や周辺の水辺空間(隅田川や浜離宮庭園)と調和させつつ、民間の活力を導入して東京の国際競争力向上にも資する持続的な街づくりを推進することが目的です。
本事業は東京都が主体となり進められ、築地市場跡地という都民共有の資産を活用するため、公募によって民間事業者コンソーシアムが選定されています。2019年3月に東京都が「築地まちづくり方針」を策定して将来像を示し、2022年11月に再開発事業の事業者募集要項が公表されました。その後の公募・審査を経て、2024年4月19日付で三井不動産株式会社を代表企業とする11社のグループ「ONE PARK×ONE TOWN」が事業予定者に決定し、2025年3月には東京都との基本協定が締結されています。これにより計画は具体的な実施段階へと進み、再開発事業の全容が明らかになりました。
本プロジェクトの総事業費は約9,000億円と試算されており、段階的に工事・開業が進められる予定です。2025年度中にもまず「先行にぎわい施設」と位置づけられる一部商業施設の着工が計画されており、遅くとも2020年代末(2028~2029年度頃)に一部施設が先行開業する見通しです。その後、2030年代前半から中頃にかけて主要施設の開業が順次進み、2030年代後半までに全体のまちびらきが完了する計画となっています。非常に長期にわたる開発スケジュールですが、東京都と事業者コンソーシアムが協力し段階的に街の姿を変えていくことになります。
築地市場跡地活用計画の詳細と現在の状況
隅田川沿いに広がる敷地に、大屋根の多目的スタジアム(中央の白い屋根)や超高層ビル群(右手)が配置され、緑豊かなオープンスペースが整備される計画がされています。一帯は水と緑に囲まれ、周辺の浜離宮恩賜庭園や築地場外市場とも調和した景観となることを目指しています。都心部にありながらウォーターフロントの開放感を感じられる、新しい「東京の顔」となる地区の誕生が期待されています。
築地市場跡地活用計画では、「ONE PARK×ONE TOWN」というコンセプトのもと、自然と都市が共生する先進的な街づくりが提案されています。隅田川や浜離宮庭園の水辺環境と築地の歴史・文化資源を活かしつつ、最先端の技術とアイデアを取り入れた持続可能な都市空間を創出する方針です。具体的には、人々が集い憩う広場や水辺空間を設けて東京ウォーターフロントの新たな「顔」となすこと、舟運(ボート交通)や「空飛ぶクルマ(エアモビリティ)」の発着にも対応できる広域交通結節点を形成して都心と臨海部の交流を促進することが掲げられています。また、築地ならではの食文化や芸術文化の発信、歴史的資源の継承にも重点が置かれており、築地場外市場のにぎわいを新街区に取り込みながら世界に向けて発信する計画です。
現在、この計画は基本協定の締結を経て詳細設計や行政手続きの段階に入っています。築地市場跡地では市場閉場後に解体工事や暫定利用(臨時駐車場など)を行ってきましたが、本格的な再開発工事に向けた準備が進められています。2025年度にはまず先行施設の着工が予定されており、敷地の一角に築地場外市場に隣接する形で商業施設や舟運拠点が建設される見通しです(この先行開発エリアは既存の場外市場に近接しており、早期ににぎわいを創出する狙いがあります)。その後、スタジアムやオフィス、ホテルといった主要施設群の建設が本格化し、段階的に街が姿を現していくことになります。現在は事業者と東京都、中央区、周辺関係者との協議が重ねられ、地域と調和した計画の詳細詰めが行われている段階です。地元中央区も「築地まちづくりの考え方」を取りまとめ、周辺地域との連携や交通基盤整備などに関する地元の意見を計画に反映させる取り組みを進めています。
開発予定施設の紹介
築地地区まちづくり事業では、商業・業務・文化・宿泊・住宅など多彩な用途を持つ複合施設群が建設されます。計画によれば、新街区には合計9棟の主要建物が整備される予定で、そこに大規模スタジアムやライフサイエンス拠点、高機能なコンベンション施設、ホテル、レジデンス(住宅)、劇場、商業施設、水上交通ターミナル等の機能が集約されます。提案概要では、最大約5万人収容の屋根付きスタジアム、ライフサイエンス分野の研究開発センター、国際会議に対応したホールや高級ホテル、日本の食文化を発信するフードホールなどが計画に盛り込まれており、これらを9つのエリアに分けて開発する構想です。さらに、東京都が計画中の新しい地下鉄ルートの駅(臨海部と都心を結ぶ新線)や、「空飛ぶクルマ」の発着ポート、舟運ターミナルなども併設し、陸・海・空を結ぶ次世代型の交通ハブ機能を持つ街になることがうたわれています。
大規模交流施設(スタジアム)は本事業の中核施設で、スポーツ大会や大型コンサートなどに対応できる収容人数5万人規模の全天候型アリーナとなる予定です。開閉式の屋根を備え、天候に左右されずイベントを開催できるのが特徴です。スタジアム内にはラウンジや貴賓室、企業向けスイートルームといったホスピタリティ施設も充実させ、国内外から訪れる観客に快適な観戦体験を提供します。また、このスタジアムは地域にも開かれた存在となる計画で、イベントのない日はコンコース(一部通路)を一般開放し、ウォーキングやジョギングができる空間として活用する構想です。屋上部には緑地を配置し、隣接する浜離宮恩賜庭園の緑と連続して眺望できる展望スペースも整備される予定で、都心にいながら自然を感じられる憩いの場ともなります。
MICE施設(国際会議場等)とホテル・レジデンス棟も計画の目玉の一つです。MICEとは大規模な国際会議や展示会などのことで、計画では1,200人規模のホールを中心とした会議場が整備されます。最新の同時通訳設備や柔軟なレイアウトが可能な多目的ホールを備え、国際学会から企業イベント、学術大会まで幅広く対応できる施設となる見込みです。併設される高級ホテルは海外からの来訪者を迎える迎賓機能を担い、上層階には長期滞在者向けのレジデンス(サービスアパートメントや高級賃貸住宅)の導入も検討されています。これら宿泊・居住機能により、国内外からの来街者が快適に滞在できる環境を整え、「昼も夜も人が集う街」の実現を目指します。MICE施設と周辺の各施設はネットワーク化され、エリア全体で数万人規模のイベントにも対応可能な体制を築く計画です。会議参加者がイベントの前後に街歩きや観光を楽しめるよう、「アフターMICE」として浜離宮庭園の拝観や築地場外市場での食べ歩きといった築地ならではの体験プログラムも提案されています。
食と文化の発信拠点も築地再開発の重要なテーマです。築地といえば日本を代表する食の街であり、その伝統を受け継ぎ発展させるため、新街区内に大規模なフードホール(飲食店街)を設ける計画です。ここでは世界中の来訪者が日本各地の新鮮な食材や郷土料理、寿司や和食といった多彩なグルメを楽しめる空間を提供し、「食の都・東京」の魅力を体感できる場とします。また、敷地内には1,200席規模のシアターホール(劇場)も整備される予定で、伝統芸能や現代演劇、ライブ公演まで幅広い演目を上演可能な文化施設となります。この劇場は地域の文化拠点として、国内外の芸術交流の場とも位置づけられています。さらに、築地場外市場から新街区へと人々の流れを誘導するプロムナード(遊歩道)が計画されています。場外市場の活気や風情をそのまま街区内に引き込み、一体的な回遊性を生み出す狙いです。このプロムナード沿いにも小規模店舗や展示スペースを配置し、築地の歴史や文化に触れられる演出がなされる見込みです。
ライフサイエンス分野の拠点も当事業の特色です。築地周辺には聖路加国際病院をはじめ医療関連施設が集積している強みを活かし、先端医療・バイオテクノロジーの研究開発拠点を新設する計画となっています。具体的には、オフィスや研究所、スタートアップ企業のインキュベーション施設などを収容する「ライフサイエンス・商業複合棟」を建設し、医療機関や大学との連携によってヘルスケア産業のイノベーション創出を目指します。また、本施設には一般向けの商業エリア(飲食・物販店)も併設され、研究者やビジネス関係者だけでなく地域住民にも開かれた賑わいをもたらす計画です。環境面にも配慮しており、隅田川の水を利用した地域冷暖房システムや太陽光発電等の再生可能エネルギー活用設備を導入することで、省エネルギー・脱炭素を推進します。敷地全体で緑被率40%を確保する大規模な緑化も計画されており、都市環境の質を高めながら持続可能な街づくりを実現する方針です。
このように、築地地区まちづくり事業では商業・業務・文化・研究・生活の各要素がバランスよく配置された「複合都市空間」を創り出す計画となっています。超高層ビルから水辺の低層施設、緑地まで多様な空間が一体的にデザインされ、一つの街の中で仕事・生活・憩い・エンターテインメントが完結するような利便性と魅力を備えたエリアになるでしょう。
地域社会・経済への影響と期待される効果
築地市場跡地の再開発がもたらす地域社会・経済への影響は非常に大きなものがあります。まず、建設段階から多数の雇用が生まれ、関連企業への経済波及効果も期待されています。事業費9,000億円規模のプロジェクトは建設業や不動産業のみならず、設計・デザイン、技術開発、サービス産業など幅広い業界に仕事の機会を創出すると見込まれます。完成後も、スタジアムイベントや国際会議の開催、新設の商業施設の運営などを通じて継続的な雇用機会が創出され、地域の経済活性化につながるでしょう。
次に、築地という立地を活かした観光振興効果が期待されます。築地は元々国内外の観光客に人気のエリアであり、特に築地場外市場には多くの外国人旅行者が訪れてきました。再開発によって整備されるスタジアムやMICE施設、フードホールや劇場といった新しい集客施設は、さらに幅広い層の来訪者を築地に呼び込むことになります。例えば、大規模コンサートやスポーツ国際大会が開催されれば全国や海外から観客が集まり、周辺のホテルや飲食店は賑わいを見せるでしょう。国際会議を開催すれば世界各国からビジネス客や研究者が訪れ、東京の魅力を発信する機会ともなります。こうした交流人口の増加は、地域の飲食業・小売業にとって大きな追い風となり、築地のみならず銀座や日本橋など周辺地域全体の経済にも波及効果をもたらすと考えられます。
また、本事業は東京の都市競争力を高める効果も狙っています。築地の再開発コンセプトには「東京を世界中から人々が集まる街にする」というビジョンが掲げられており、ウォーターフロントの魅力と最先端の都市機能を備えた築地新街区は東京の新たなランドマークとなることが期待されています。都心部にこれだけの大規模複合開発が実現する例は近年でも限られており、完成すれば 「東京の玄関口」 の一つとして国内外にアピールできる存在になるでしょう。例えばニューヨークのハドソンヤード開発やロンドンのカナリーウォーフのように、都市再生プロジェクトが成功すればその都市全体のブランド力向上につながります。築地も同様に、再開発の成功によって東京の国際都市としての評価をさらに高め、将来的な企業誘致や観光誘客に寄与することが見込まれます。
地域社会への効果として忘れてはならないのが、周辺住民の生活環境の向上です。従来の築地市場は早朝からトラックが行き交い混雑する面もありましたが、新しい街では歩行者デッキの整備による歩車分離や交通結節点の強化により、安全で快適な歩行者空間が確保されます(計画では敷地2階部分に広大な歩行者デッキを設け、地上は車両動線とすることで人と車の動線を分離します)。広場や緑地など市民が自由に利用できる公共空間も増え、地域住民の憩いの場・交流の場として機能するでしょう。さらに、商業施設の充実により日常の買い物の利便性も高まることが予想されます。特に築地エリアはこれまで生鮮食品市場としての性格が強く、大型商業モール等は近隣に多くありませんでした。再開発で多彩なテナントが入る商業ゾーンが誕生すれば、地元住民は遠くまで出かけなくとも身近で買い物や外食を楽しめるようになります。総じて、本事業は地域にもたらす経済波及効果と暮らしやすさの向上という両面で、大きなプラスをもたらすと期待されています。
不動産市場への影響(価格動向、投資観点など)
築地の再開発計画は、都心不動産市場にも大きなインパクトを与えています。まず、土地価格の上昇期待です。広大な築地市場跡地が高度利用されることで周辺エリアの地価も押し上げられるとの見方があり、実際に再開発発表後は築地周辺の地価に強含みの傾向が見られます。専門家からは「築地再開発による地価の上昇期待」を背景に、築地エリアに本社を置く企業への注目度が高まる可能性が指摘されています。再開発のニュースを受けて投資マネーが関連不動産や周辺企業の株式に流入する動きも報じられており、マーケットは築地エリアの価値向上を織り込みつつあるようです。
実際の地価動向データも再開発への期待を反映しています。例えば東京都の地価調査によれば、中央区築地三丁目付近の基準地価は2024年に前年比+16.6%という大幅な上昇を記録しました。同じ中央区内でも銀座エリアに匹敵する伸び率であり、築地エリアへの投資需要が高まっていることがうかがえます。築地市場移転直後の一時期は地価が停滞した面もありましたが、再開発計画が具体化したことにより将来の収益期待が高まり、不動産市況が活気づいています。周辺ではマンション開発やホテル進出の計画も報じられており、再開発効果で築地周辺エリア全体の不動産価値が底上げされる可能性があります。
投資の観点では、本事業は民間コンソーシアムにとっても極めて大型のプロジェクトであり、参画各社が将来的な収益機会に期待を寄せています。三井不動産をはじめとする大手デベロッパーが9000億円規模の投資を決断した背景には、都心一等地の創出による長期的な賃料収入や資産価値の向上が見込めることがあります。オフィスや商業テナントの誘致による賃料収入、ホテル・イベント事業による収益、住宅分譲や不動産売却益など、多面的なリターンが期待できるでしょう。特に築地は銀座や日本橋と隣接する好立地でありながら、これまで大規模オフィスビルが少なかったエリアです。再開発により最新鋭のオフィス空間が供給されれば、国内外企業の新たな進出ニーズを取り込み、東京のオフィスマーケットにも良い影響を与えるかもしれません。
一方、これだけの巨大開発ゆえに不動産市場への影響が慎重に見極められている側面もあります。東京湾岸エリアでは近年超高層マンションの大量供給などで市況の変動もみられましたが、築地プロジェクトは用途が商業・業務中心で住宅は限定的であるため、住宅市況への直接的な供給影響は小さいとみられます。それよりも、再開発によってエリアのブランド力が高まることで周辺中古マンションや商業ビルの評価額が上昇する、いわば資産価値の底上げ効果がメインになるでしょう。不動産投資家にとっては、築地・銀座・晴海周辺のエリア全体が「再評価」され、将来的な値上がり益(キャピタルゲイン)を見込んだ投資対象として魅力を増すという見方が出ています。
一般消費者にとってのメリット(住環境、利便性向上など)
築地地区まちづくり事業は、一般消費者である都民や来街者にとって様々なメリットをもたらします。まず第一に、生活環境の改善が挙げられます。再開発後は大規模市場に代わって整備された道路網や歩行者空間により、築地周辺の交通混雑が緩和され安全性が高まるでしょう。計画にはバリアフリー化された歩行者デッキや広場が含まれており、高齢者や子供連れでも安心して歩ける街になります。また緑地やオープンスペースが増えることで、都心にいながら季節の自然を感じられる憩いの場が身近に提供されます。従来の築地市場は一般の人が気軽に立ち入れる場所ではありませんでしたが、新街区では誰もがアクセスできるパブリックスペースが整備され、市民に開かれた交流の場が生まれる点は大きなメリットです。
利便性の向上も重要なメリットです。現在、築地周辺の公共交通は日比谷線築地駅や大江戸線築地市場駅が最寄りですが、再開発に合わせて計画されている地下鉄新線の新駅が実現すれば、東京駅方面や臨海副都心方面へのアクセスが飛躍的に向上します。都心~湾岸部を結ぶ新路線が開業すれば、築地はまさに東京の交通ハブの一角となり、通勤・通学や買い物の利便性が高まるでしょう。加えて、水上バス(舟運)ターミナルが新設されることで、浅草やお台場方面への観光船による移動も楽しめるようになります。将来的に「空飛ぶクルマ(エアタクシー)」が実用化されれば、築地はその発着拠点ともなり得ます。こうした次世代モビリティサービスの導入は、一般消費者の移動手段の選択肢を広げ、快適で魅力的な都市体験につながるでしょう。
新たに整備される商業施設群も、一般消費者に大きな恩恵をもたらします。従来の築地場外市場は専門的な食材店や飲食店が中心でしたが、再開発地区にはファッション・雑貨・日用品など多様なテナントを含む近代的なショッピングモールの要素が加わる可能性があります。これにより、築地地区で日常的な買い物が完結し、周辺住民の生活利便性が高まります。また、大規模イベント施設ができることで、都民は遠方へ出かけなくとも地元でスポーツ観戦やコンサート鑑賞ができるようになります。家族連れで週末にスタジアムや劇場のイベントに気軽に足を運べるようになれば、娯楽の選択肢が増え生活が豊かになるでしょう。イベント開催時以外でも先述のようにスタジアムの一部が市民に開放される計画があり、仕事帰りや休日にジョギングや散策を楽しめるなど、日常的な健康増進や余暇活動の場としても利用できます。
さらに、築地再開発は防災面でのメリットもあります。最新の耐震・防災設備を備えたビル群の建設により、地域の防災拠点機能が向上し、大規模災害時には避難場所や帰宅困難者の受け入れ場所として活用されることが想定されています。オープンスペースや舟運拠点は災害時の物資輸送や避難経路としても役立つ可能性があります。老朽化した市場施設があった頃に比べ、街全体の安全・安心のレベルが高まるのは地域住民にとって大きなメリットです。
このように、築地地区まちづくり事業は一般の人々にとって身近な暮らしやすさと都市の魅力の両方を高めてくれるプロジェクトだといえます。新しい築地の街は、住む人にも訪れる人にも優しく快適な、誰もが楽しめる空間となることでしょう。
今後の課題と展望
築地再開発事業は多くの期待を集める一方で、その実現に向けた課題も指摘されています。まず、計画のスケールと長期性そのものが課題です。2030年代後半まで続く長期間の開発プロジェクトとなるため、その間の社会情勢や経済状況の変化に柔軟に対応していく必要があります。計画段階の提案内容も今後の協議で変更される可能性があり、事業者は情勢の変化に応じて臨機応変にプロジェクトを進化させることが求められます。特に、大規模イベントの需要見通しや国際会議の開催状況など、コロナ禍を経た社会でどう推移するか不確実性があります。スタジアムやMICE施設の稼働率を高く維持し収益を上げていくためには、魅力的なイベントを誘致し続ける営業努力や、新たなエンターテイメントコンテンツの開発が不可欠でしょう。コンソーシアムには読売新聞社やトヨタ不動産といった異業種企業も参画しており、メディア発信力やモビリティ技術といったそれぞれの強みを活かして街の魅力創出に取り組む姿勢が示されています。こうした異分野の連携をうまく機能させ、長期にわたるプロジェクトを牽引していくマネジメント力が問われています。
次に、交通インフラ整備の実現性も課題です。計画で触れられている地下鉄新線(いわゆる「臨海地下鉄」構想)は東京都が検討を進めていますが、実際の着工・開業時期は未定であり、多額の事業費や国の認可プロセスなどハードルがあります。再開発地区の完成に新線整備が追いつかない場合、スタジアムイベント開催時の交通混雑やアクセス面の課題が懸念されます。逆に新線が開業すれば築地の価値は飛躍的に高まりますが、鉄道整備という外部要因に本プロジェクトの成功の一部が左右される点はリスクともいえます。東京都と関係機関には、新線を含めた交通基盤強化を着実に進めるとともに、開業前提でなくとも既存交通網で混雑を捌けるよう計画段階から対策を講じることが求められます。具体的には、シャトルバスや水上バスの充実、周辺道路の改良、駐車場・駐輪場の整備などソフト・ハード両面の対応が課題となるでしょう。
また、地域との調和も重要なテーマです。築地という土地は長年市場関係者と地元住民が共存し独自のコミュニティを築いてきた経緯があります。再開発によって街の景色や人の流れが大きく変わる中で、地元商店や住民の生活が疎外されないよう配慮する必要があります。中央区が地元の意見を集約し東京都に提言するなど取り組んでいるように、今後も行政・事業者・地域住民の三者が密接に連携して課題を共有し解決策を講じていく姿勢が求められます。例えば、築地場外市場の既存店舗との共存策や、再開発エリアと周辺街区との段差解消など細かな点まで丁寧に対応することで、「新旧が共生する築地」を実現していくことが理想です。歴史ある波除神社や場外市場の風情と、近未来的な新街区とが調和する光景は、東京ならではの多層的な魅力となるでしょう。そのためにも、地域文化の継承と最新都市機能の調和という難しい課題に挑む姿勢が重要です。
最後に、経済性と公共性のバランスも課題と言えます。民間主導の事業である以上、事業収支の確保は欠かせませんが、一方で都民共有の財産である土地を活用する以上、公共性も重視されねばなりません。現在示されている計画は観光・ビジネスの振興と環境・文化の調和に配慮した内容ですが、今後の具体化の過程で経済合理性との折り合いをつける局面が出てくる可能性があります。その際に短期的な収益より長期的な公共的価値を重視する判断が求められる場面もあるでしょう。例えば緑地や広場の維持管理コスト、文化施設の採算性などは課題となり得ますが、官民協働で工夫しながら街の価値を高めていくことが大切です。
以上のような課題はありますが、総じて見ると築地地区まちづくり事業は東京の未来像を体現する非常に魅力的なプロジェクトです。ウォーターフロントに広がる新しい都市空間は、多くの人々に愛され利用されることで真価を発揮するでしょう。今後10年以上にわたる長丁場の事業ではありますが、節目ごとに部分開業しながら段階的に街が育っていくプロセス自体も都民にとって楽しみと言えます。築地の地に息づいてきた伝統と、最新のテクノロジーやアイデアが融合するこの街が、無事に完成し繁栄する未来を展望しつつ、我々一般消費者も長期的な視点で見守りたいものです。その先に、東京の新たなシンボルとして世界に誇れる「築地」の姿が再び生まれることを期待したいです。

稲澤大輔
INA&Associates株式会社 代表取締役。大阪・東京・神奈川を拠点に、不動産売買・賃貸仲介・管理を手掛ける。不動産業界での豊富な経験をもとに、サービスを提供。 「企業の最も重要な資産は人財である」という理念のもと、人財育成を重視。持続可能な企業価値の創造に挑戦し続ける。 【取得資格(合格資格含む)】 宅地建物取引士、行政書士、個人情報保護士、マンション管理士、管理業務主任者、甲種防火管理者、競売不動産取扱主任者、賃貸不動産経営管理士、マンション維持修繕技術者、貸金業務取扱主任者、不動産コンサルティングマスター

.png)